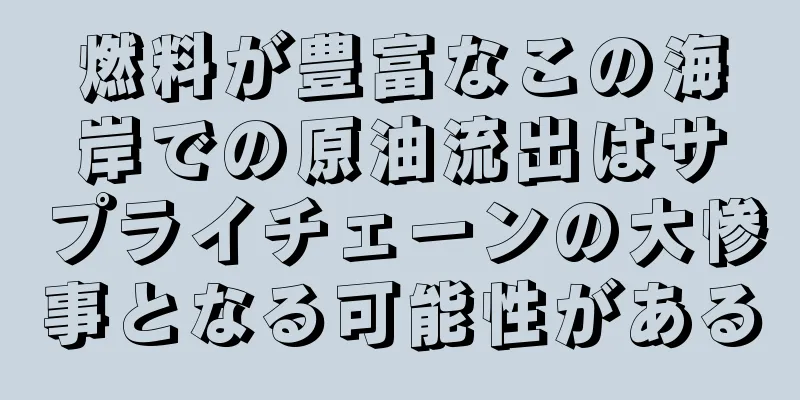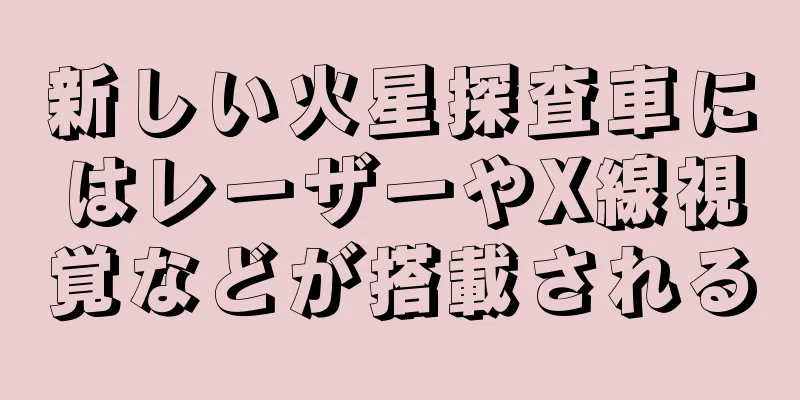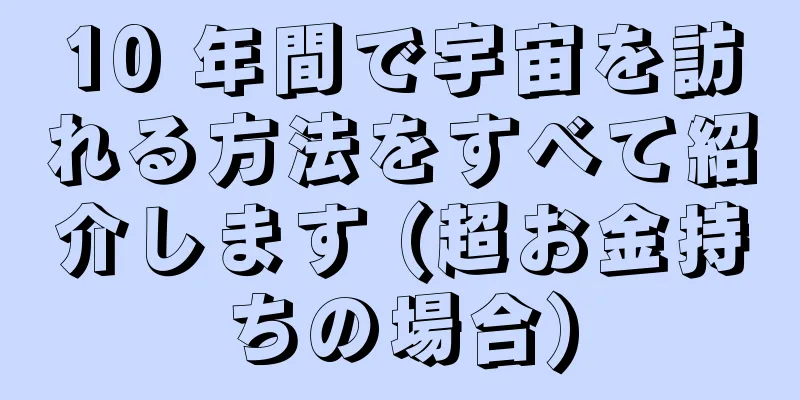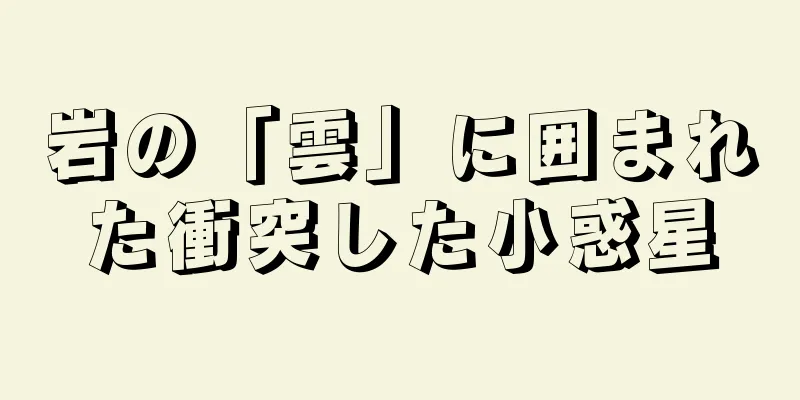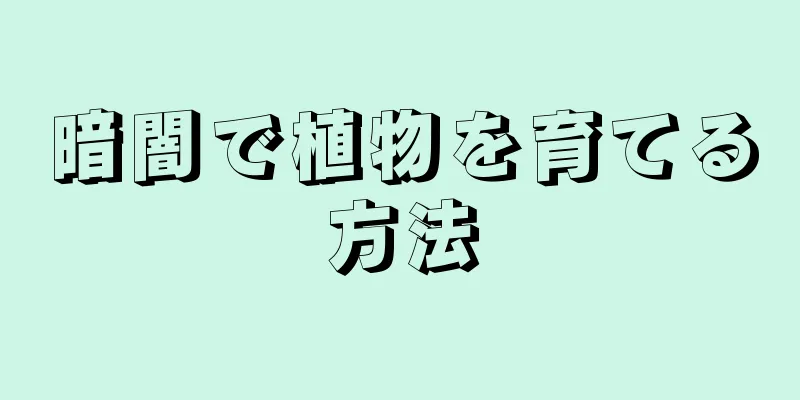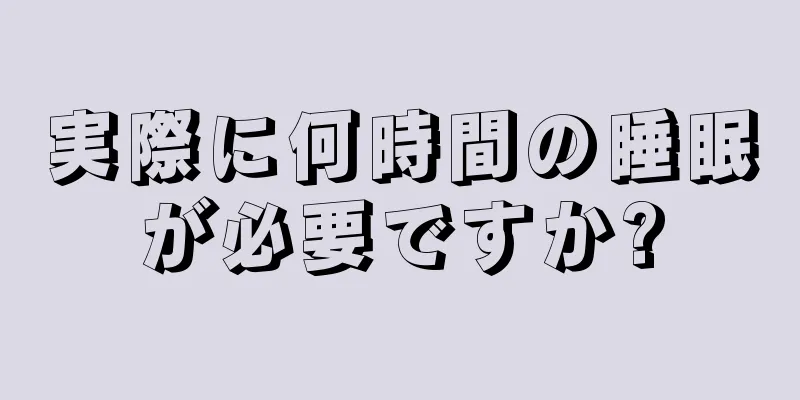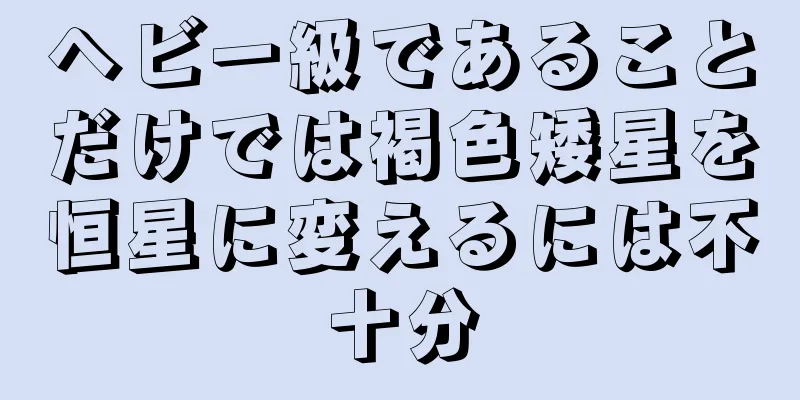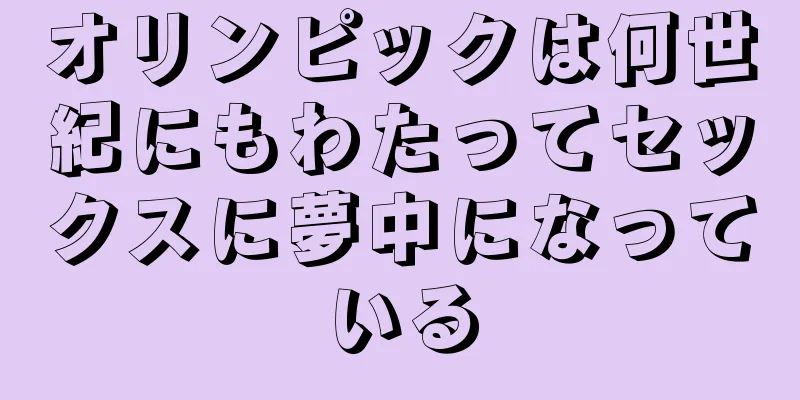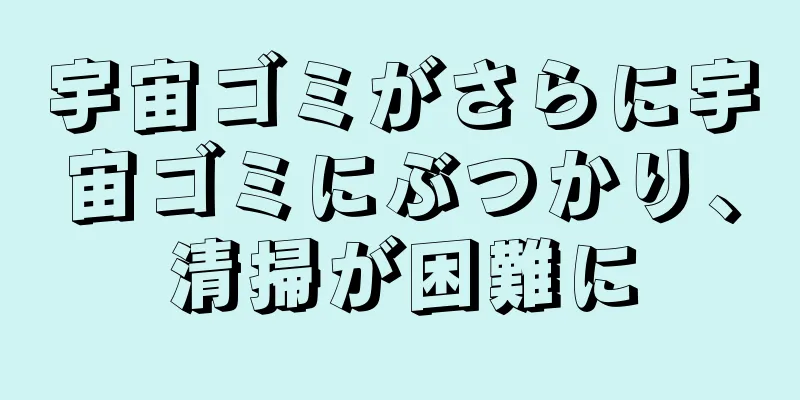なぜ鳥肌が立つのでしょうか?
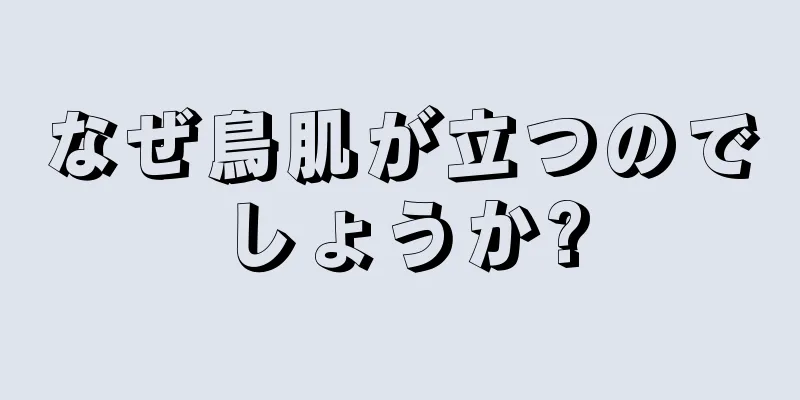
|
予期せぬ冷たい風、自分の足につまづきそうになったとき、歌手がとびきり高い音を出した時。これらはすべてまったく異なる経験ですが、共通点が 1 つあります。それは、鳥肌が立つことです。しかし、鳥肌とはいったい何で、なぜ鳥肌が立つのでしょうか。科学者は最初の疑問についてはよく理解していますが、なぜ鳥肌が立つのかは、まだ謎に包まれています。 鳥肌について最もわかりやすいのは、その名前です。ガチョウの羽をむしり取ったばかりのとき、羽毛があった場所に皮膚に隆起した隆起ができます。人間に鳥肌ができるメカニズムも非常に単純です。毛根と呼ばれる皮膚に最も近い毛束の先端には、立毛筋と呼ばれる小さな筋肉があります。これらの筋肉が緊張したり、収縮したりすると、毛がまっすぐに逆立ちます。 驚くべきことに、科学者たちは鳥肌が立つ理由を完全には理解していません。しかし、それはおそらく先祖から受け継いだ生存メカニズムだと考えています。人類の系統のどこかで、私たちは今よりもずっと太くて長い毛に覆われていました。初期の人類が寒くなると、毛が少し持ち上がり、離れていました。これにより、皮膚の近くに少量の空気が閉じ込められ、効果的に断熱層が形成されました。 それはすべて完全に理にかなっています。しかし、美しい音楽の音のような楽しいことを体験すると、なぜ私たちは鳥肌が立つのでしょうか? ユタ州立大学の研究者、ミッチェル・コルバー博士は、寒くないときに鳥肌が立つ理由を研究している。具体的には、皮膚を駆け巡る快感の波である「ゾクゾク感」を研究している。これは、人類の3分の2が感じる感覚だ。 彼によると、最新の理論では、これは闘争・逃走反応の一部であり、予期せぬ音などの刺激に数ミリ秒以内に反応する生来の生存メカニズムだという。たとえば、夜に森を歩いているときに近くで木の枝が折れる音を考えてみよう。考えなくても、その折れる音はすぐに私たちの体をアドレナリンの放出に導き、呼吸、発汗、脈拍の上昇を促す化学物質だ。こうした身体的反応はすべて、私たちの体を行動(逃走、またはいわゆる闘争)に備えさせる。 アドレナリンは鳥肌も立たせる。コルバー氏は、人間の脳は生きていくために非常に細かく調整されており、棒が折れる音を予期するという先祖伝来の習慣が音楽や芸術の体験にも引き継がれていると語る。 「熟練した歌手の声帯は、音程を合わせて叫ぶように訓練されています。そのため、歌うときの声帯の振動の一部は、誰かが大声で叫んでいるときの振動に似ています」とコルバーは言います。音楽を聴いていて、曲の中で予期せぬこと (高音、コードの変更) が起こり、闘争・逃走反応が起こったとします。何かがおかしい! 鳥肌が立ちます。いったん認知能力が働き、落ち着いて芸術を楽しむように指示されると、闘争・逃走反応は停止します。この経験から、幸福感を誘発する化学物質であるドーパミンが大量に分泌されることもあります。 コルバー氏は、その音をもはや警告の音として感じることはなく、美しく心地よいものとして認識している、と語る。「それはまるで、何かが脅威ではないと気づいたことに対して、進化が私たちに報いるかのようだ」 |
>>: 病気の従業員を家に留まらせることで、レストランは多額の費用を節約できる可能性がある
推薦する
最大速度
人間も機械も、かつてないほどのスピードで未来に近づいています。ほぼ毎年、私たちの乗り物は速度記録を更...
アカボシチョウはどうなっているのでしょうか?
バージニア州中央部からニューイングランド南部にかけてのどこかに住んでいるなら、おそらく間近でその群れ...
火星に小さな植民地を作るには、地球に残された愚か者たちを
火星に持続可能な居住地を建設するとなると、技術的、工学的な課題は山積しています。しかし、人事部門にと...
古代のソーシャルネットワークが陶器のトレンドを世界中に広めた
ライフハック、猫の動画、疑わしい健康アドバイス、陰謀論がソーシャルメディアを席巻する何千年も前から、...
これらの古代の海生爬虫類は非常に速く大きくなった
約2億4600万年前、ザトウクジラとほぼ同じ体長の海生爬虫類が、現在のネバダ州の海域を巡回していた。...
アメリカの国立公園ドキュメンタリーシリーズによると、自然保護における人々の役割
「思い出だけを持ち帰り、足跡以外は何も残さない」という格言は、ドゥワミッシュ族のシアール酋長、または...
スティーブン・ホーキング、ブラックホールのパラドックスの「内部を解明」することを目指す
ブラックホールに落ちたらどうなるでしょうか?この質問は面白いだけでなく(理論によってはスパゲッティに...
プエルトリコのアレシボ天文台が稼働し、近くの小惑星を発見した。
それは誰もが考えていたよりも大きかった。今月初め、天文学者が地球近傍小惑星3200フェートンの高解像...
TEDは好きじゃなかったけど、その後理解できた
今年は、文化的な漫画、権力の交差点、そして影響力の工場であるTEDに初めて参加した年でした。私はキャ...
NFLチームの中には、時代遅れの知能テストに基づいてクォーターバックをドラフトするチームもある
このストーリーはもともと The Conversation に掲載されました。クォーターバックのトゥ...
ダイヤモンド量子ビットは室温で約2秒間データを保持します
量子コンピューターを構築するには、科学者はまず、制御可能かつ測定可能な実用的なキュービット、つまり量...
ボニエコーポレーションプライバシーポリシー
ボニエコーポレーションプライバシーポリシーこのポリシーは 2018 年 5 月 16 日に最終更新さ...
なぜニキビを潰すことがそれほどまでに満足感を与えると感じる人がいるのか
典型的なニキビは、皮膚の皮脂腺の詰まりや細菌が原因です。ほとんどのニキビは無害ですが、特に外部環境に...
ボーンズ・ディープ
ポピュラーサイエンスでは今週はスター・トレック週間。7月22日の劇場公開『スター・トレック BEYO...
ヨーロッパ人はネアンデルタール人を軽蔑していたが、DNAが共通していることに気付いた。
私たちは永遠に自らの起源を追い求めています。現在、欲しいものが見つからないとき、私たちは過去に戻り、...