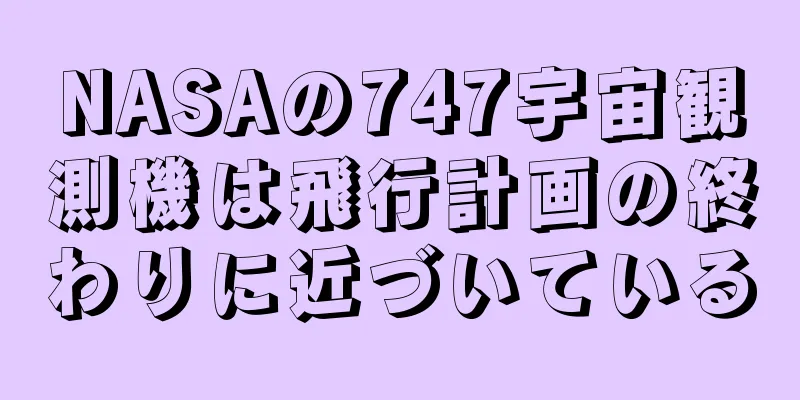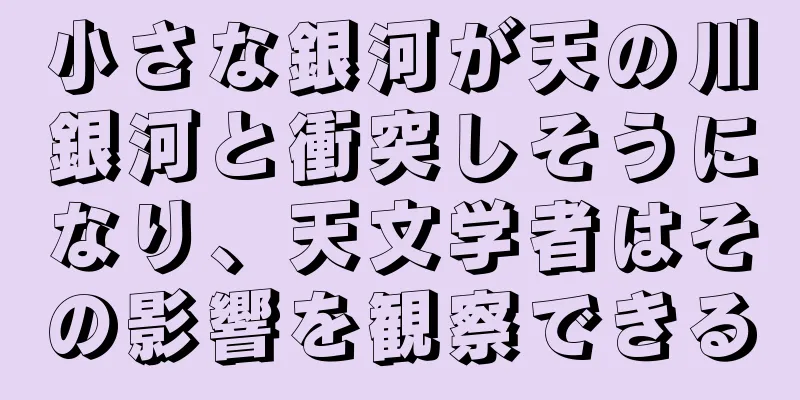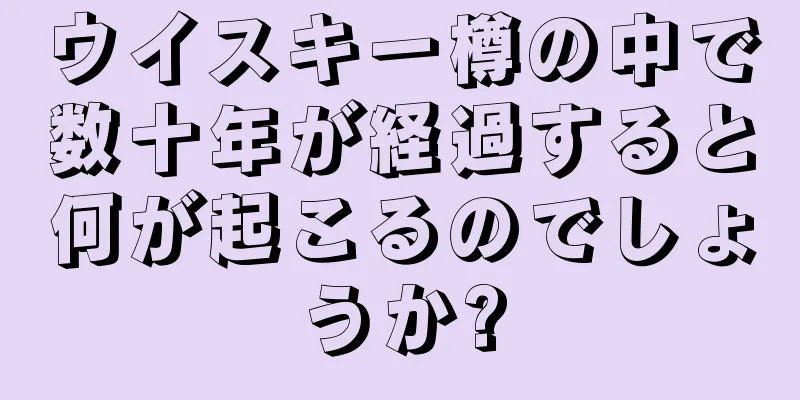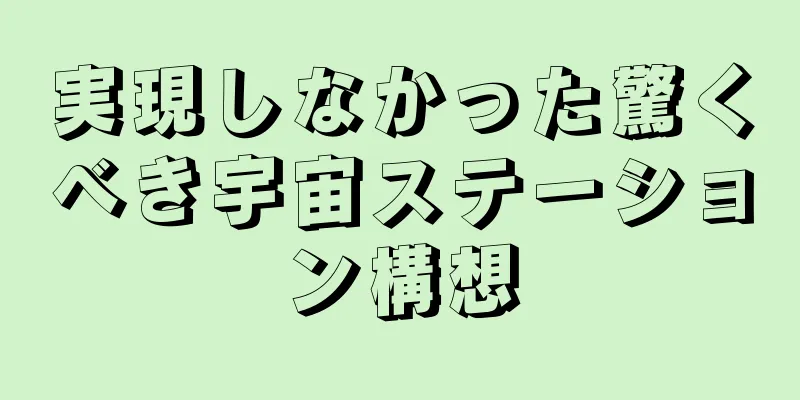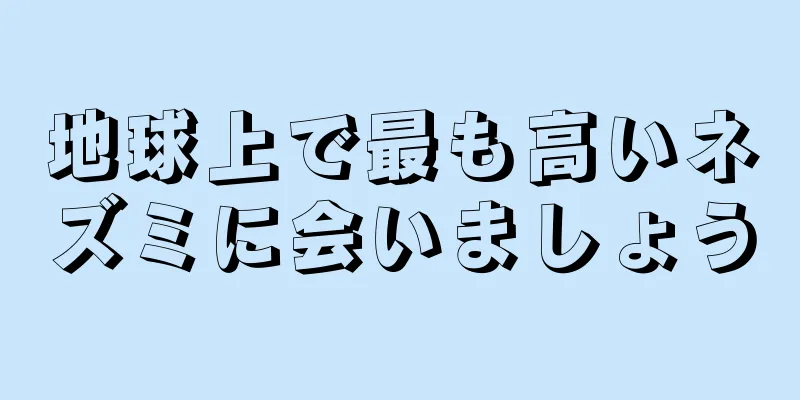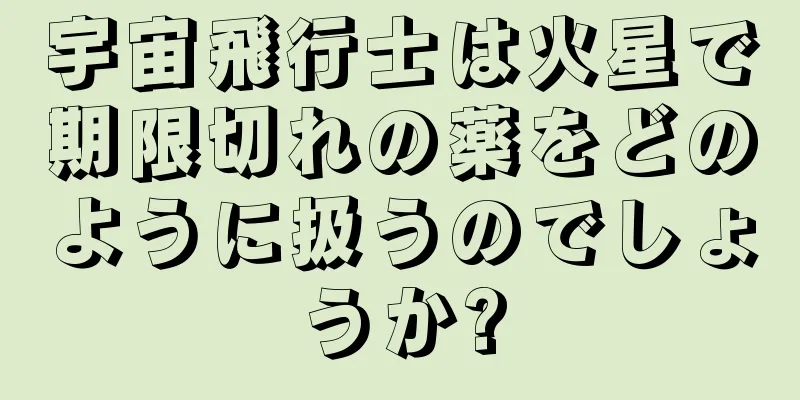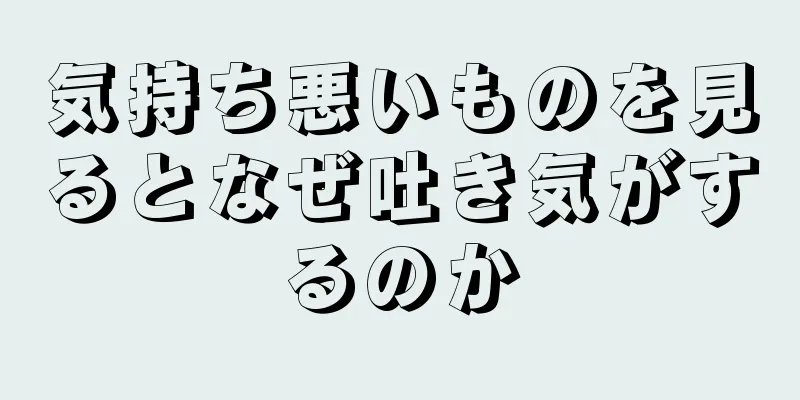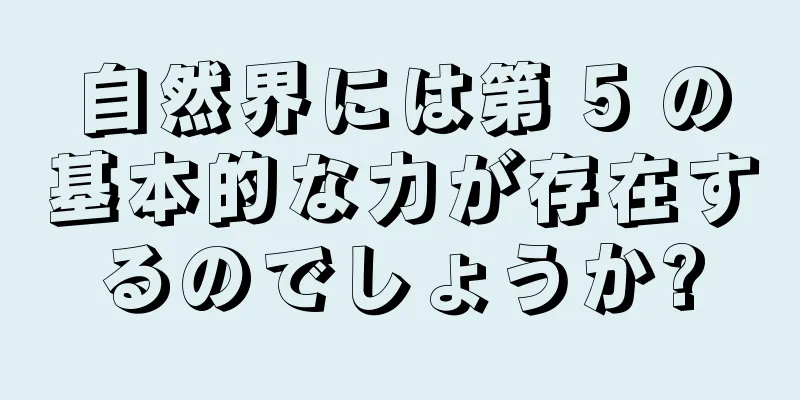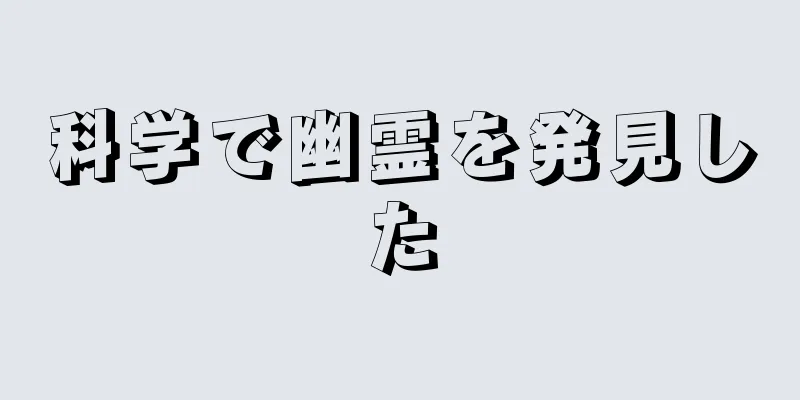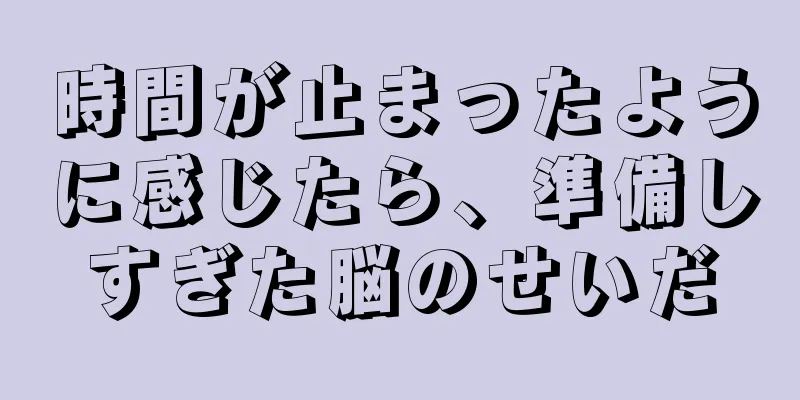爬虫類と両生類は若返りの泉の鍵を握っているのでしょうか?
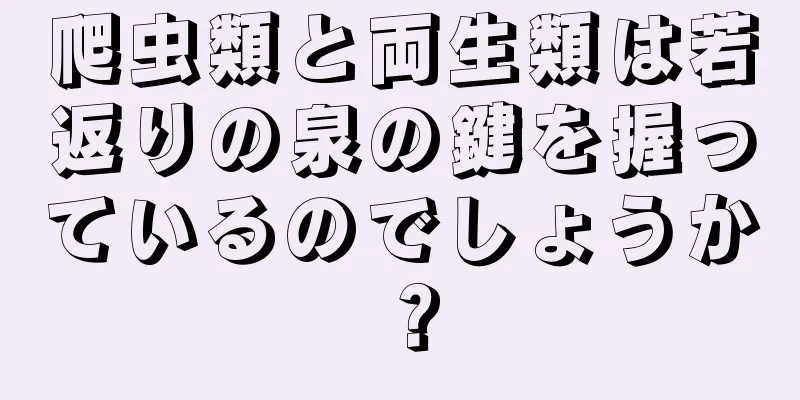
|
長寿に関しては、科学者たちは長い間、うろこがありぬるぬるした脊椎動物が優れていると考えてきた。ガラパゴスゾウガメ、トウブハコガメ、洞窟に住むサンショウウオの仲間であるオルム、その他多くの爬虫類や両生類は、100年以上生きることができる。そして、陸上動物として知られている最高齢のジョナサンという名のセイシェルゾウガメは、最近190歳の誕生日を迎えた。 しかし、これまで、これらの動物の寿命の長さを裏付ける証拠のほとんどは、動物園からの逸話的な報告から得られたものだと、シカゴのノースイースタンイリノイ大学の生物学者ベス・ラインケ氏は言う。彼女と世界中の100人以上の研究者のチームは、野生の爬虫類と両生類77種の老化速度を比較した。この研究はもともと、カメは長生きできるという長年の考えから生まれた。「私たちは、それがどの程度広く信じられているのか知りたかったのです」とラインケ氏は言う。 研究者らは、老化と寿命は種によって大きく異なるものの、カメ、ワニ、サンショウウオは一般的に老化が非常に遅く、体の大きさに比べて寿命が不釣り合いに長いことを発見した。一方、デンマークの別の研究者グループも、動物園や水族館で飼育されているカメやリクガメ52種を比較して同様の結論に達した。爬虫類の約75%は老化が遅いかほとんどなく、80%は現代人よりも老化が遅いという。 両チームは6月23日、サイエンス誌に研究結果を発表した。オックスフォード大学の生態学者で、この研究には関わっていないロブ・サルゲロ・ゴメス氏は、新たな発見は特に驚くべきものではないが、老化(生物が性成熟に達した後に身体機能が徐々に低下し、死亡リスクが上昇する現象)が普遍的であるという考えに疑問を投げかけるものだと語る。 「どちらも素晴らしい研究です」と彼は言う。「生命の樹全体にわたる老化についての理解に、新たな一面を加えてくれるのです。」 ラインケ氏と共同研究者は、カメ、カエル、サンショウウオ、ワニ、ヘビ、トカゲ、トカゲに似たムカシトカゲなど、多種多様な動物を対象とした長期にわたる研究を参考にして分析を行った。これらの研究では、爬虫類と両生類の個体群を平均17年間にわたって追跡し、19万匹以上の動物を調査対象とした。 種がどれだけ早く老化するかを判断するために、ラインケ氏と彼女のチームは、性成熟に達した後の個体の死亡率を計算した。チームは、これらの成体動物の95パーセントが死亡するまでにかかった年数から寿命を推定した。 ラインケ氏は、これらの推定値の注意点として、研究者らが死因を区別していない点を指摘する。「『老化』と聞くと、人は生理学的なことだけを考える傾向があります」と同氏は言う。「私たちの老化の測定には、生理学的なことだけでなく、野生で死をもたらす可能性のあるすべてのことが含まれます。」 [関連: これらのクラゲは死を免れているようです。その秘密は何でしょうか?] 研究チームはまた、自分たちの推定値を、哺乳類や鳥類の老化に関する以前に発表されたデータと比較した。これらの脊椎動物のグループは温血動物または内温動物であり、つまり体温を自分で調節することができる。ラインケと研究チームは、冷血動物または外温動物の爬虫類と両生類は代謝が遅いため体の生理的消耗が少ないため、鳥類や哺乳類よりも全体的に老化が遅いだろうと予想していた。しかし、結果はまちまちだった。爬虫類と両生類の中には、ほとんどの鳥類や哺乳類よりも老化が遅いものもあれば、老化が速いものもあった。爬虫類と両生類の寿命は1~137年と幅広く、霊長類の4~84年よりはるかに幅が広い。 しかし、爬虫類や両生類の系統樹全体に老化がほとんどない種が現れ、カメ類はグループとして「特に老化が遅い」と彼女は言う。 保護用の殻、うろこ状の装甲、あるいは毒を持つ種は、老化が遅く、寿命も長かった。爬虫類と両生類の両方において、遅くから繁殖を始めた種は結局長生きした。研究チームはまた、温暖な気候に生息する爬虫類は老化が早いのに対し、同様の環境にある両生類は老化が遅いことも観察した。 これらやその他の変数が老化や寿命の違いにどのように影響するかを解明するには、さらなる研究が必要です。「私たちが明らかにした非常に興味深いパターンは数多くあり、さらに調査する必要があります」とラインケ氏は言います。「外温動物は、人間の健康にとっての老化について知りたいことの多くに対する答えを持っていると思います。」 人間の寿命を延ばすという探求において、サンショウウオは特に有望なグループかもしれない。「サンショウウオの多くは10年以上生きます。大きさを考えるとかなり長いです」とラインケ氏は言う。この両生類は、失った手足や尾を再生する能力で有名で、一部の科学者は、この再生能力とサンショウウオの驚異的な長寿の間には関連があるのではないかと考えている。 2番目の新しい論文では、デンマークの研究チームは飼育されている爬虫類の老化に焦点を当てた。 「老化に関するこれらの理論はすべて、性成熟後、細胞の損傷や組織の修復に多くのエネルギーを費やすのをやめ、生殖に多くのエネルギーを費やすようになると、死亡リスクは加齢とともに増加すると述べている」とオーデンセにある南デンマーク大学の生物学者で、この研究結果の共著者であるリタ・ダ・シルバ氏は言う。 老化による有害な影響から逃れられる可能性のある種として最も有力なのは、カメやリクガメのように生涯を通じて成長し続ける種である。 「私たちが主に関心を寄せていたのは、例えば人間や他の哺乳類、鳥類と同様に、カメの死亡リスクが加齢とともに増加するかどうかです」とダ・シルバ氏は言う。彼女と同僚は、飼育されているカメやリクガメの記録を分析した。各種のデータは58匹から数千匹に及んだ。 ほとんどの種では、死亡率は年齢とともに一定か、または実際に減少した。平均すると、オスのカメやリクガメはメスよりも長生きした。これは哺乳類で見られるものとは逆である。研究チームは3種の野生個体群のデータも調査し、飼育下の動物は老化率が低いことを発見した。 「何らかの方法で、これらの個体群は条件が整えば老化速度を低下させる方法を見つけたのです」とダ・シルバ氏は言う。飼育下では爬虫類は餌や住処を探すのにエネルギーを注ぐ必要がない。しかし、なぜ一部の爬虫類だけがこの恵みに反応して老化を最小限に抑えたり避けたりするように見えるのかは明らかではない。「他の種にとっては、条件が理想的ではないか、老化を止めることができないかのどちらかでしょう」とダ・シルバ氏は推測する。 [関連: 若返りの泉はずっと私たちの血の中にあったのでしょうか?] 研究対象となったカメやリクガメの種の大半は人間よりもゆっくりと老化するが、この研究結果が人間の健康と老化を理解する取り組みにどのような影響を与えるかを判断するのはまだ時期尚早だ。 「こうした比較をする際には注意が必要です」とダ・シルバ氏は言う。「これと人間の間に明確なつながりを見いだすことはできませんが、老化のメカニズムの理解に一歩近づいたと言えます。」 サルゲロ・ゴメス氏は、この2つの新しい論文は、老化についてまだ解明されていないことがどれほど多く残されているか、また老化が人間と他の動物、植物、さらに遠縁の生物の間でどのように異なるかを示していると語る。 「この種の研究には、生物医学研究への潜在的応用を超えて、生命の樹における私たちの位置をより深く理解し、すべてが人間の生き方に従うわけではないという認識を得るという真の価値がある」と彼は言う。 |
>>: 大型ハドロン衝突型加速器(LHC)の稼働再開初日に学んだこと
推薦する
85年前に「農家の少年」がいかにして冥王星を発見したか
1930年6月号の『ポピュラーサイエンス』で、私たちはこの100年近くで天文学において最も重要な発見...
ボーイングの苦戦中のスターライナー機は少なくとも2024年までは宇宙飛行士を乗せない
ボーイング社のスターライナー宇宙船は、7月21日に予定されていた有人試験飛行で先月地球を出発する予定...
この古代の恐竜の親戚は、驚くほどワニに似ている
テレオクレーター ラディヌスアルゼンチン科学自然博物館化石の奥深くまで見ることができるレーザースキャ...
PopSciの冬号があなたのために準備完了
毎年、 PopSci のスタッフが集まって特集テーマについてブレインストーミングするとき、スタッフ全...
死にゆく人間の脳の記録から何がわかるか
医師らは初めて、突然死の前後の詳細な脳波活動を収集した。研究者らは、その解釈の中で、人生は確かに「目...
火星で生命を見つけるには、新しい探査機、より高性能な探査車、そして人間が必要だ
これは一定のサイクルです。NASA は、記者会見で火星に関する新しいニュースが発表されるとプレスリリ...
NASA の奇妙で球根状のスーパー ガッピー貨物機がアラバマ州に着陸する様子をご覧ください
半世紀以上も忠実に任務を果たしてきた世界で最後のスーパー ガッピー機は、巨大なヒンジ付き貨物室で N...
トロオドンは現代のダチョウと同じように共同の巣で卵を産んだ
鳥が空に飛び立つ前に曲がった脚で飛び回る様子を見るのは、進化の時計を巻き戻して獣脚類恐竜を観察するよ...
科学者たちは「エイリアンの巨大構造の星」の長年の暗化について何も知らない
KIC 8463853 という星には暗い秘密がある。文字通りだ。2011 年と 2013 年に、この...
カロリーとは何ですか?
カロリーの定義は簡単そうです。ほとんどの科学の教科書によると、カロリーとは 1 グラムの水の温度を ...
柔らかい毛皮を持つハリネズミの新種5種が特定された
ハリネズミの系統樹は2023年を終え、さらにいくつかの枝が加わる。12月21日にリンネ協会動物学ジャ...
この神秘的な古代の石板は、数学について何かを教えてくれるかもしれない
一部の研究者は、バビロニア人が三角法を発明し、しかもそれをより優れたものにしたと言っている。メソポタ...
音波で作られたトラクタービーム
トラクター ビーム (「アトラクター ビーム」の略で、遠くにある物体を別の物体に近づけることができる...
米国では100万回分以上のサル痘ワクチンが出荷される予定
サル痘は第二のパンデミックには程遠いものの、世界中の保健当局が警戒を強めている。月曜日の時点で、サル...
ハインツの新しい「マーズ」ケチャップは、火星のトマトから作られたようなものだ
宇宙農業の最新の進歩は、火星のような環境で栽培されたトマトから作られたケチャップという形で現れました...