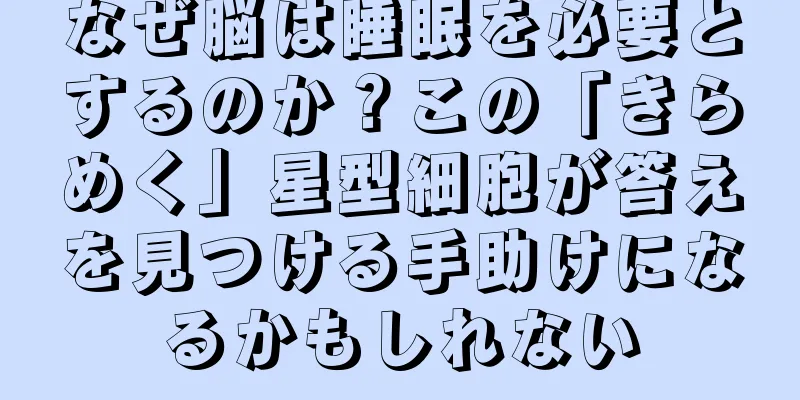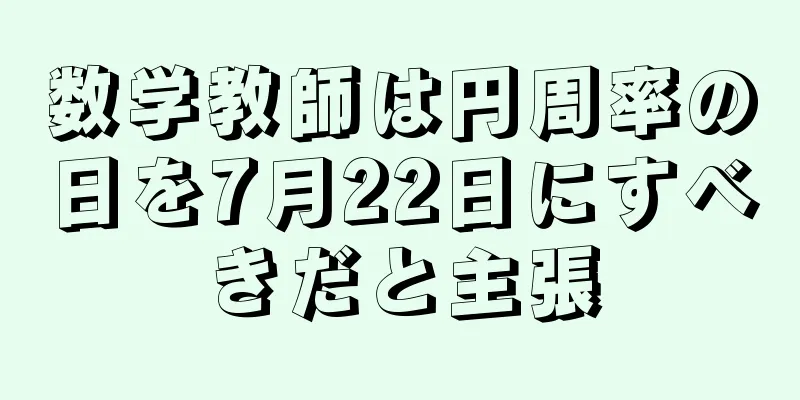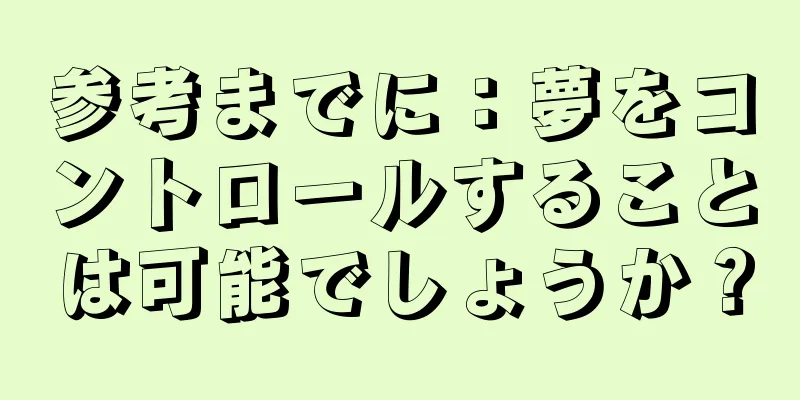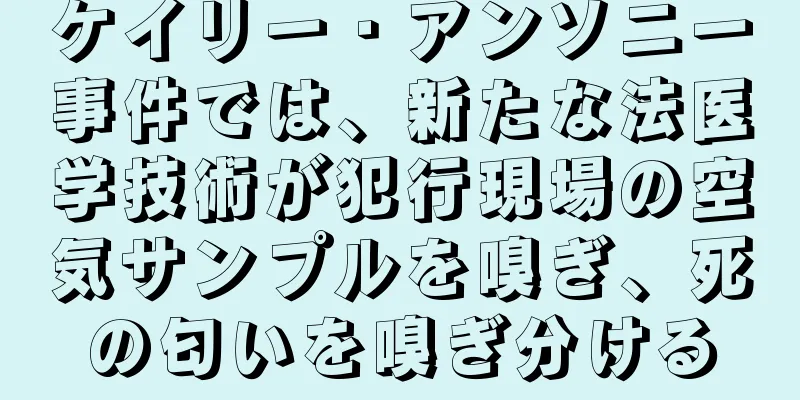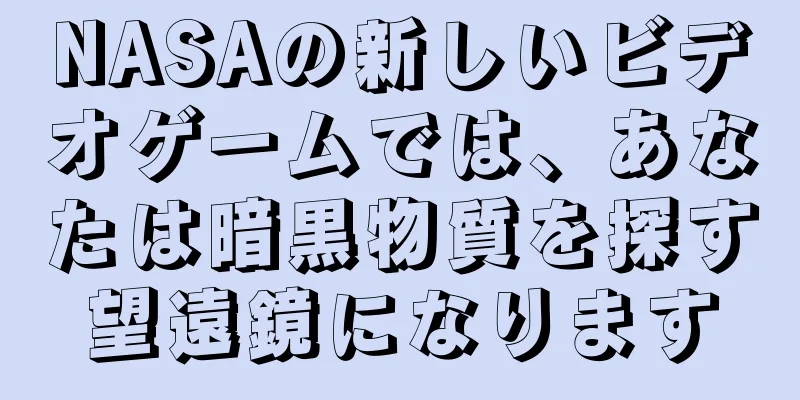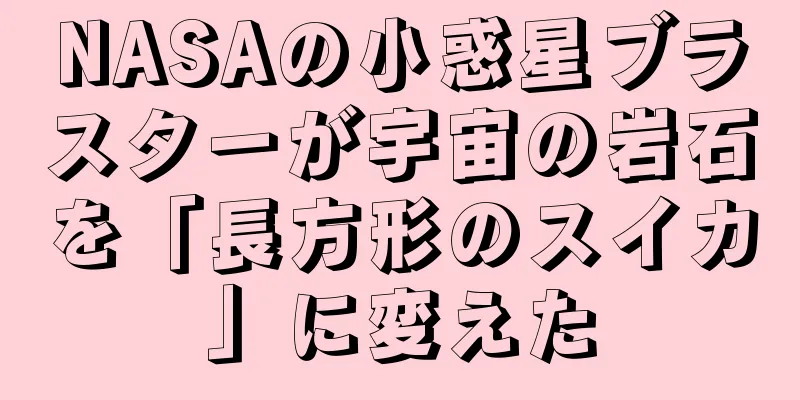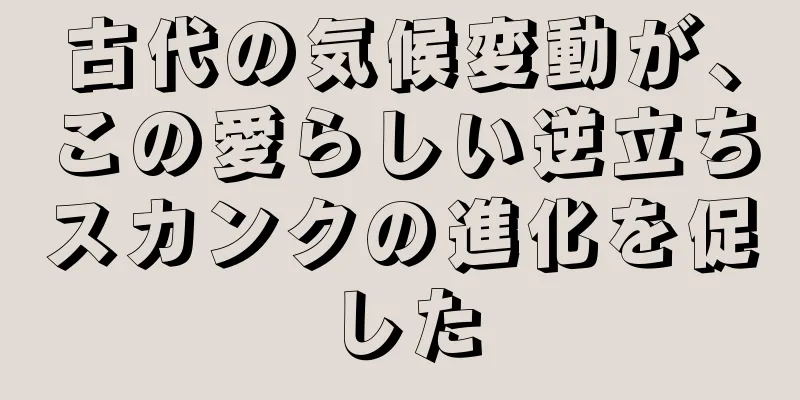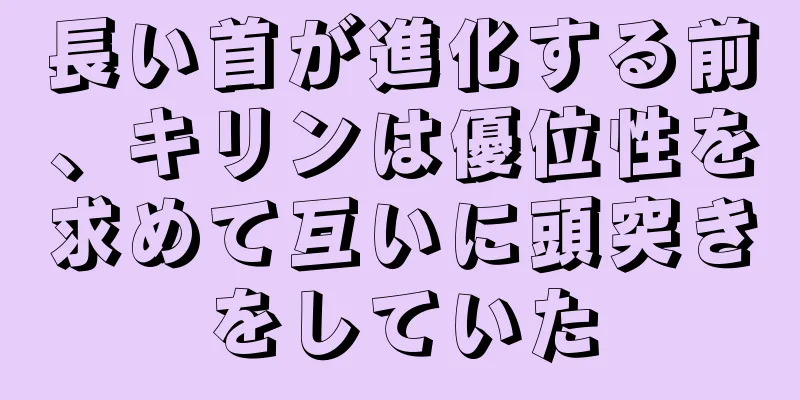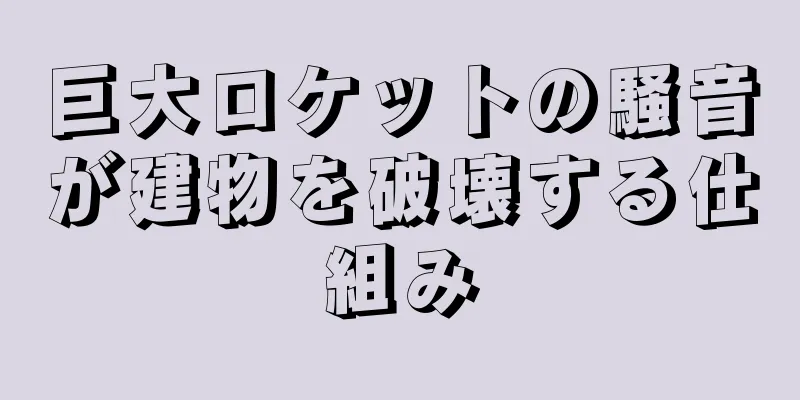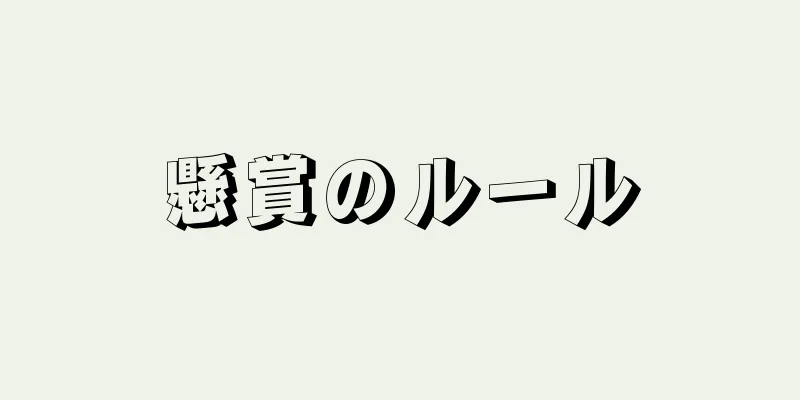人類が火星に行くとしたら、着陸するのに最適な場所はどこでしょうか?
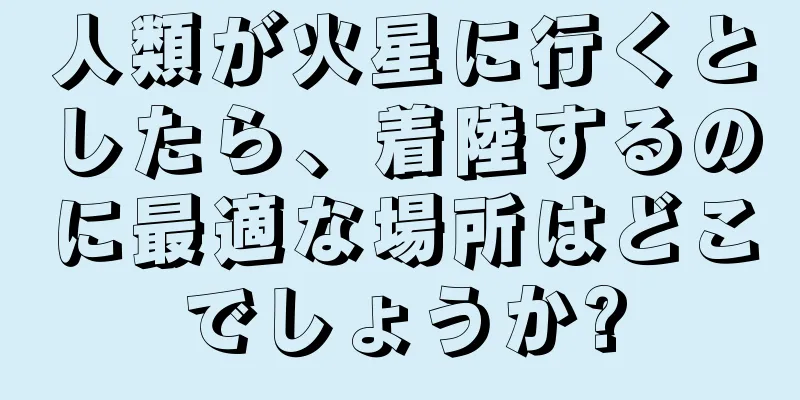
|
映画『オデッセイ』では、取り残された宇宙飛行士が過酷な火星で生き延びなければならない。今週、科学者たちは、宇宙飛行士が実際にいつか着陸する可能性のある火星の場所を特定するための初のワークショップを開催する。 今日ワークショップが始まると、分析中の50以上の場所のうち、遠い惑星の生命にとって最も適した場所はどこなのかという議論が激しくなるかもしれない。たとえば、ヘブルス渓谷の地下洞窟の地下住居か、かつては生命が存在していたかもしれないグセフクレーターの温泉近くの基地か。そして、この会議に参加する科学者の多くは、いつか自分たちも火星に行くことを望んでいる。 「将来訪れるかもしれない着陸地点を選んでいるところです」と、火星への片道旅行を提案する「マーズ・ワン」ミッションの最終候補100人の一人であるニューメキシコ大学の惑星科学者ザカリー・ガレゴス氏は言う。 「いつか火星を歩く最初の人間になるのが私の夢です」と、ノースカロライナ州ローリーのカーディナル・ギボンズ高校の10年生で、惑星科学者と火星探検家を目指すアレックス・ロンゴさんは付け加えた。 着陸地点火星探検家がまず必要とするのは、安全に着陸できる場所だ。ガレゴス氏は、目標は、数回のミッションで多くの補給船や乗組員船を着陸させるのに適した、およそ25キロメートルの平坦な地域だと語る。 「さらに、岩だらけのものは避けてください。岩は着陸に危険を及ぼし、移動を困難にします」とNASAジェット推進研究所の惑星科学者フレッド・カレフ氏は言う。「しかし、非常に柔らかいものも避けてください。火星には数メートルの深さの塵の塊がある場所もあり、ふわふわした粉の上に着陸するのは避けたいでしょう。」 低高度では「上空の大気が厚くなるため」、着陸地点としても適している可能性があるとカレフ氏は言う。空気が多ければ、パラシュートやその他のブレーキ機構を使って安全に着陸しやすくなる。 ローカルリソース火星での宇宙飛行士の生活は、火星にすでに存在する資源の利用に大きく依存する。宇宙探査ではこれを「現地資源利用」と呼ぶ。宇宙飛行士が火星で収集したいと望む最も重要な資源はおそらく水だろう。水は飲料水としてだけでなく、放射線遮蔽物として、また水素と酸素に分解すれば燃料としても役立つ。「地球から火星に水を運ぶコストはかなり高い」とカレフ氏は言う。 火星には水源が 5 つある可能性がある。氷床、水分を豊富に含む含水鉱物、地下帯水層、技術的には反復斜面線として知られる季節的な水の流れ、そして大気の湿度である。「これらのうちどれが最良の水源であるかについては、激しい議論が交わされるだろう」と、NASA 科学ミッション局の科学探査担当副局長リチャード・デイビス・ジュニア氏は言う。 火星での水源として最適なのは氷床と水和鉱物かもしれないとデイビス氏は言う。一見すると、水源として最も明白なのは氷床かもしれないが、火星は非常に寒く、「氷が冷たくなるほど、氷は硬くなる。地面から岩のように固い氷を掘り出して溶かすには、多くのエネルギーが必要になる」とカレフ氏は言う。それでも、水を得るには砂や岩を浚渫し、水が出るまで焼く必要があり、これには氷床を溶かすよりも多くのエネルギーが必要になると一般的に考えられている。水源としてどの選択肢が最適かを知るには、さらなる研究が必要だとデイビス氏は言う。 火星人になる人たちが必要とするかもしれない他の重要な資源は、建設資材用の砂利、砂、岩石です。「土は放射線遮蔽物として居住地に積み上げることができます」とガレゴス氏は言います。「丸石や大きな岩は、サービス道路の建設や維持に使用できます。岩や鉱物から金属やシリコンを精製して、さまざまな目的に使用できます。」 素晴らしい景色もちろん、宇宙飛行士は火星に着陸して生活したいだけでなく、地元の名所、つまり科学的発見がなされるかもしれない場所も訪れたいと思うでしょう。 『オデッセイ』でマーク・ワトニーは火星で生き延びるために全力を尽くしましたが、実際の宇宙飛行士は赤い惑星で過去、あるいは現在も生命の痕跡を探すかもしれません。 火星での宇宙飛行士の主な科学的焦点はおそらく水だろう。「NASAは水と有機物を追跡し、現在または古代の生命の痕跡が見つかるかもしれない場所へ行きたいと考えています」とカレフ氏は言う。「水が集まり、有機物が保存されている可能性のある、残存する池の堆積物や古い河川デルタなど、過去に居住可能だった環境を訪問したいのです。」 宇宙飛行士は古代の水域だけでなく、繰り返される緩やかな線状地形、水氷霧、地下帯水層の兆候など、現在の水活動にも注目するだろう。これらは「火星の現存する生命の探索にとって非常に興味深いものとなるだろう」とカー氏は言う。 クレーター、露頭、峡谷、砂丘などの地質学的特徴は、火星の地質学的歴史を明らかにするものとなるでしょう。クレーター、露頭、峡谷、砂丘などの地質学的特徴は、火星の地質学的歴史を明らかにすることが期待されています。このような特徴は宇宙飛行士にとってナビゲートするのが難しいかもしれませんが、「これらは通常、惑星科学者が研究したい種類の特徴です」とガレゴス氏は言います。 火星の宇宙飛行士は、着陸地点の近くでのみ発見を行うことに限定されるわけではない。「乗組員は着陸地点から最大100キロ離れた場所まで移動できるほどの機動力を持つことが期待されています」とNASAの有人探査・運用部門の主任探査科学者ベン・バッシー氏は言う。 赤道か、それとも他の場所か?ワークショップに出席する科学者たちの間での主な分かれ目の一つは、彼らが有人ミッションを赤道付近で提案するか、それとももっと高緯度で提案するかということだろう。 「高緯度地点に着陸する主な利点の 1 つは、特に北部の平原で水に簡単にアクセスできることです」とビオラ氏は言います。「地表の最上部 1 メートル以内に氷があることがわかっているので、宇宙飛行士は地表下深くまで掘る必要がありません。この氷は比較的きれいな状態なので、人間の乗組員を支えるのに十分な水を得るために広い地域を開拓する必要もありません。」 「さらに、水氷は潜在的に重要な科学的ターゲットになると思います」とヴィオラ氏は言う。「水氷は堆積した当時の火星の気候の記録を保存している可能性があり、地球の氷床コアを使って地球の気候の歴史を知ることができるのと似ています。また、水氷には過去または現在の生命の証拠が含まれている可能性もあります。」 しかし、高緯度地域は「居住するには極めて困難な場所となるだろう」とロンゴ氏は言う。「冬の間、宇宙飛行士たちは何ヶ月も太陽を見ることができず、乗組員の士気に悪影響を及ぼし、エネルギー源としてのソーラーパネルを失うため、基地は完全に原子力で動かなければならないだろう」。高緯度地域では冬の間、気温が低くなるため、機器にも負担がかかる。 「赤道付近の探査地域では、地球上と同様に、年間の直射日光がより多く当たることになります」とガレゴス氏は言う。「NASA の有人火星探査構想では、原子力エネルギーを主な動力源として利用していますが、多くの小規模な基地や装置は太陽光発電で稼働する必要があります。」 最後に、マーズワンの候補者のように宇宙飛行士が火星への片道旅行をするのでない限り、彼らは地球に帰還するための打ち上げに適した場所を必要とするだろう。「火星で打ち上げに最適な場所は赤道です。惑星は赤道上でより速く回転し、打ち上げ機の速度が上がるため、ロケット燃料をそれほど必要としません」とカレフ氏は言う。(このような速度上昇のため、ヨーロッパの宇宙港は地球の赤道近くのフランス領ギアナに位置している。) それでも、赤道付近の発射場の方が打ち上げは容易だが、「ただそれだけの理由で、そのような場所に限定されるべきではない」とデイビス氏は言う。「ケープカナベラルとヴァンデンバーグ空軍基地はどちらも米国の発射場であり、赤道からそれほど近い場所ではありません。科学と資源が許すところに行くべきです。」 ベストサイト火星に人間が着陸するのに最適な場所は、探査機が事前に偵察した場所だとカレフ氏は主張する。「探査機の着陸地点は平らで安全であることは誰もが知っています。私たちはそれらの場所について大量の科学的情報を収集しています」とカレフ氏は言う。「火星についてもっと知るためにどこへ行き、どこを掘削するかについて推測する必要はほとんどありません。火星の岩石がどのようなものか、どこに追加の調査が必要なのかがわかっています。」 ロンゴ氏は、これまでに探査された場所のうち、スピリット探査車が通過したグセフクレーターが、人類の探査にとって最も刺激的な可能性があると主張する。「私の見解では、スピリットがグセフクレーターで発見したような古代の熱水環境は、将来のあらゆるミッションにとって最も重要な科学的ターゲットです」とロンゴ氏は言う。「地球上の温泉は生命の住処であり、生命が誕生した理想的な場所である可能性もあります。」 もう一つの可能性は、キュリオシティ探査車が探査したゲールクレーターだ。「ここでは、火星の地質学的歴史における、湿潤火星と乾燥火星の間の大きな変遷を見ることができます」とカレフ氏は言う。「また、高度が低いため、空気のクッションが多く、着陸に有利です。」 ガレゴス氏も、ゲイル・クレーターは人間による探査には魅力的な選択肢だと考えているが、「以前の場所に戻ることのデメリットは、新しい場所を研究できないことです」と同氏は言う。「研究すべき場所は地球全体なので、別の場所を訪れるべきだと言う人もいるかもしれません」。デイビス氏はまた、探査機が探査した場所の多くは乾燥している傾向があり、居住の試みを複雑にする可能性があると指摘する。 ゲールクレーターとグセフクレーターはどちらも赤道上にある。ロシア科学アカデミーの惑星科学者ゲンナジー・コチェマソフが赤道上にある可能性のある場所として挙げているのが、映画『オデッセイ』でワトニーが住んでいた場所であるアシダリア平原だ。さらにもうひとつはマリネリス峡谷で、「ここは何十年も着陸地点として提案されてきた」とガレゴスは指摘する。「この巨大な峡谷は火星を横切って4,000キロメートル以上伸びており、火星の地質学的、水文学的過去を垣間見ることができる」。マリネリス峡谷には、地表の下に液体の塩水があることを示唆する傾斜線が繰り返し見られると、MITの科学者でエンジニアのクリストファー・カーは言う。 巨大な隕石クレーターであるヘラス平原の東端には、古代の火星の地殻と大きな水氷の塊が存在します。より高緯度にあるプロトニルス・メンサエは、複雑な台地と谷のネットワークの一部であり、「氷河の形で大量の水氷が含まれていることがわかっています」とガレゴス氏は言う。「私は、モリュー・クレーターの真東にあるプロトニルス・メンサエ地域に探査ゾーンを提案しました。このゾーンは、火星の古代の地殻だけでなく、火星のさまざまな化学体制と時代間の遷移を記録している岩石ユニットへのアクセスを提供します。」同様に、彼は、巨大な隕石クレーターであるヘラス平原の東端にある「メソポタミア」には、人間の探検家にとって有用な古代の火星の地殻と大きな水氷の塊があることを指摘している。 とはいえ、火星で生活するのに最適な場所は、表面ではないかもしれない。コーネル大学の宇宙生物学者アルベルト・フェアレン氏とその同僚は、地下の洞窟が完璧な住居になる可能性があると示唆している。 「火星は地球の2年ごとに太陽の周りを一周するため、地球から火星への往復の2回の打ち上げ間隔は2年になります。したがって、探査隊は必ず火星に2年間滞在することになります」とフェアレン氏は言う。「乗組員が火星で2冬を乗り切るには、表面の放射線や極端な温度変化から身を守るための非常に本格的なシェルターを用意する必要があります。これらの要件を妥当なコスト、エネルギー、労力で達成する唯一の方法は、地表の下に潜り込んで隠れることです。」 古代の壊滅的な洪水は、ヘブルス渓谷の洞窟網の形成を助けました。この地域には、地下の水氷と生命の化石があるかもしれません。「洞窟や溶岩洞などの地下環境を人間の探査用シェルターの建設拠点として提案した数十の提案のうち、私たちの提案だけが唯一のものであることに気付き、大きな驚きを感じました」とフェアレン氏は言います。「地下は、火星の人類探査を開始する唯一の選択肢のようです。」 このワークショップは、人類が火星に着陸する可能性のある場所についての最終的な決定ではありません。「その決定に向けて、私たちが本当に大きな第一歩を踏み出していることは素晴らしいことです」とカレフ氏は言います。「目的地を選び始めると、これは空想から現実になります。」 |
推薦する
NASA の無料ストリーミング プラットフォームが今週開始されます。視聴できるコンテンツは次のとおりです。
ストリーミング サービスの月額サブスクリプション料金がどんどん高くなり、観たいものを探すのに映画の上...
これは火星探査機スピリットが見た最後の画像です
NASA の擬人化の試みにもかかわらず、火星探査車は話さないので、スピリットは最後の言葉を発すること...
なぜ大きな音でくしゃみをする人がいるのでしょうか?
私がくしゃみをすると、みんなにそれが伝わります。その結果生じる衝撃波で窓が揺れ、眠っている動物が目を...
最新情報: ヨーロッパの火星探査ミッション、1つの勝利と1つの大きな可能性
東部時間午後3時30分更新:欧州宇宙機関は、本日早朝に火星の大気圏に突入した着陸機との接触を確認しよ...
月着陸船オディはまだ死んでいない
横向きに着陸し、電力供給に苦労したにもかかわらず、半世紀以上ぶりに月面に着陸した米国の宇宙船「オデュ...
討論: スタートレックで最高の医療担当官は誰ですか?
金曜日に『スター・トレック:ビヨンド』の公開が迫っているため、ポピュラーサイエンスでは今週はスター・...
眼球に関する新たな研究が時差ぼけの治療法につながるかもしれない
体内時計は、おそらく体内で最も信頼できる機械です。体内時計は、睡眠から代謝まで重要な機能を調節するた...
テレプレゼンスは忘れてください!ついに嗅覚プレゼンスが登場
ニュースサイト「ロケットニュース24」によると、日本の着パフューム社は「サイバー空間を越えて匂いを届...
雨粒がはじけると、空気中にバクテリアが飛び散る。それはとても美しい。
本日、ネイチャー・コミュニケーションズ誌に発表された研究によると、雨滴が細菌を空中に放出している可能...
中国の民間宇宙産業はスペースXやブルーオリジンとの競争に備える
米国では、最近の宇宙旅行に関するメディアの注目は、華やかな億万長者や民間企業の活動に集中している。し...
これらのバイキングの女性たちは尖った頭の流行を起こそうとしたが、それはうまくいかなかった
今週あなたが学んだ最も奇妙なことは何ですか? それが何であれ、 PopSciのヒット ポッドキャスト...
太陽系最大の溶岩湖を間近で見ることができました
地球上の溶岩湖は巨大な溶岩の塊で、絶対にゴミを捨ててはいけません。(注意:溶岩湖に飛び込むのもやめて...
スコットランドで新たな翼竜の種が発見される
英国の古生物学者がスコットランドのスカイ島で新種の翼竜を発見した。この爬虫類はおよそ1億6800万年...
科学者が「未来のフィンチ」の鳴き声をシミュレート
エクアドルのガラパゴス諸島を故郷とするフィンチは、チャールズ・ダーウィンの進化論の重要な証拠を提供し...
BeerSci: ビールの苦味はどうやって測るのでしょうか?
数週間前、BeerSci チームは、お気に入りの醸造所の 1 つであるペンシルバニア州ダウニングタウ...