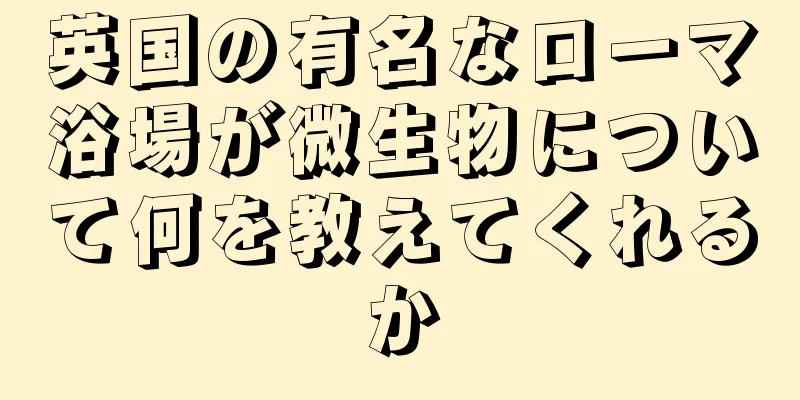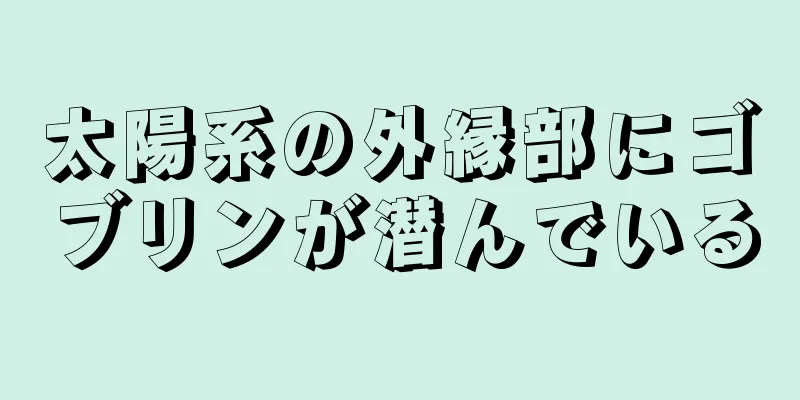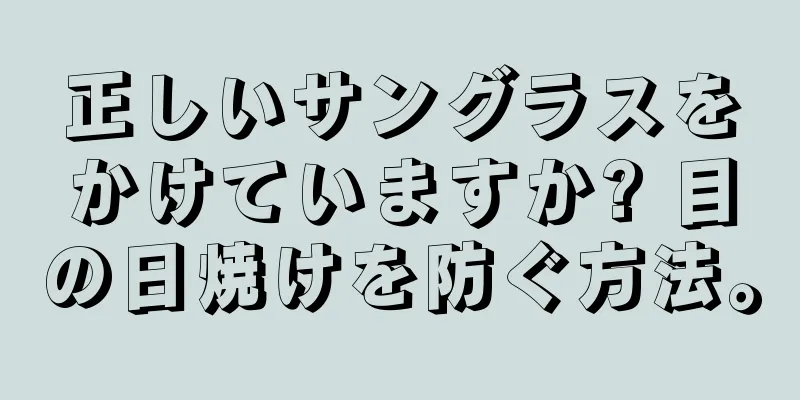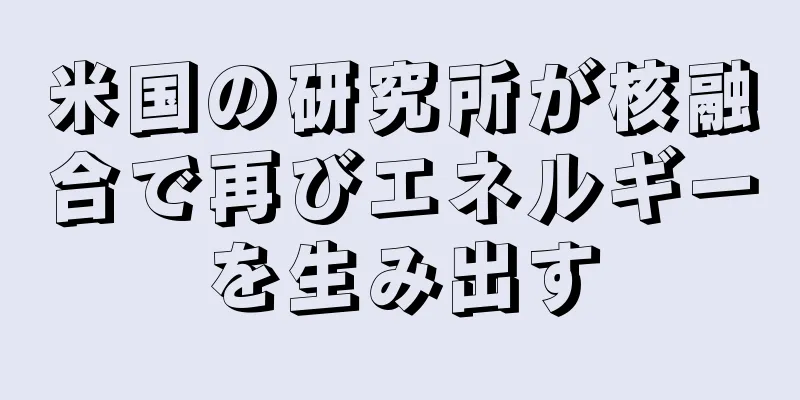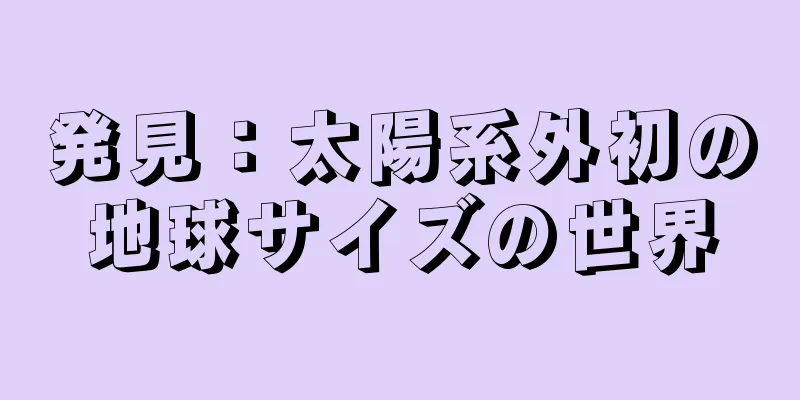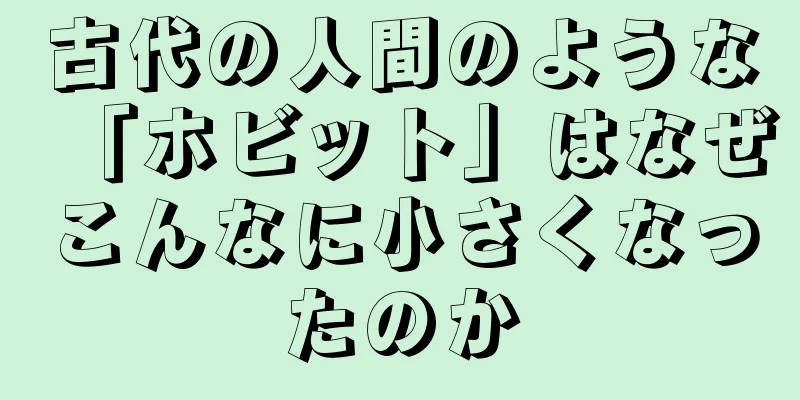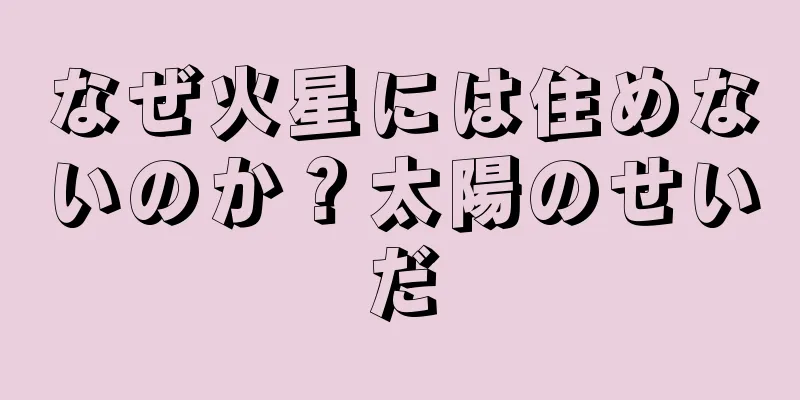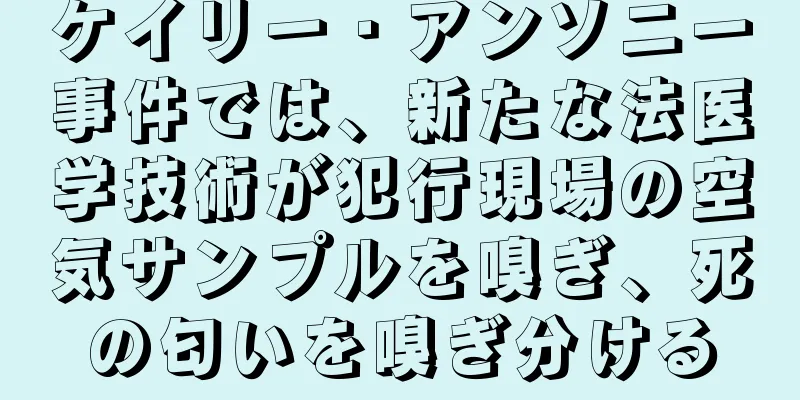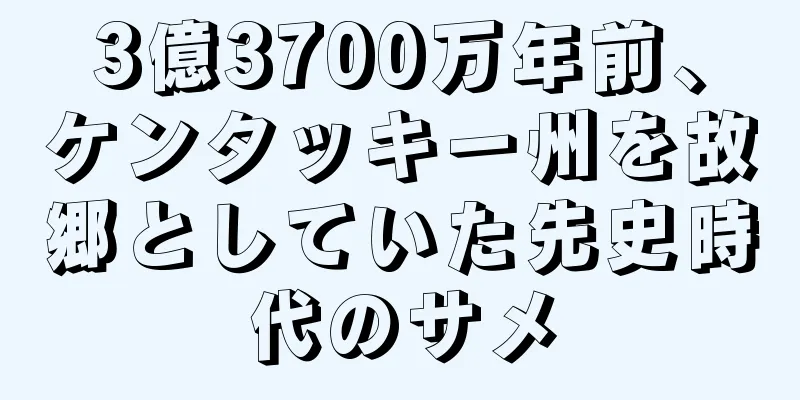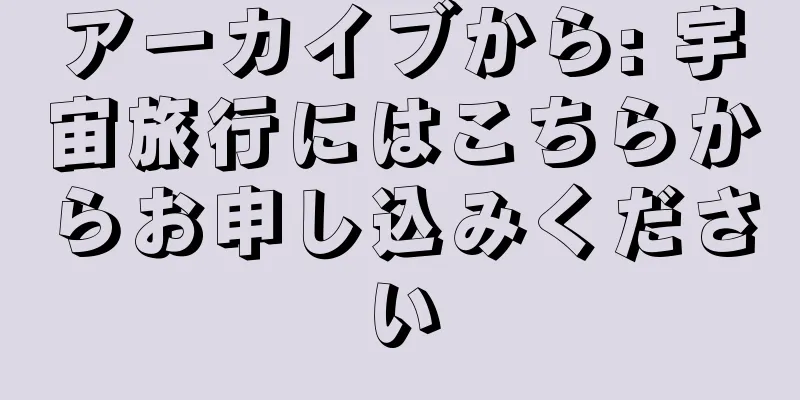動物は死に対してどう反応するか:徹夜から人食いまで
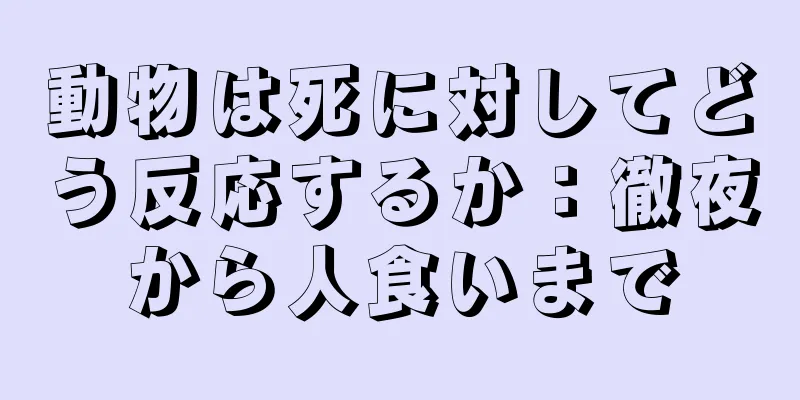
|
人生において必然性はほとんどありません。その 1 つ (ごくわずかな例外を除く) が死です。特定の種類の淡水ポリプや奇妙なクラゲでない限り、誕生は死の保証です。人間は、この厳しい生物学的現実に対処するために、数千年も前から独自の複雑な対処戦略を開発してきました。考古学的発見の中には、人間の死の儀式がホモ サピエンスより古く、ネアンデルタール人やその他の絶滅した古代人類に埋葬や葬儀の習慣があったことを示す証拠さえあります。しかし、動物界の他の動物はどうでしょうか。人間以外の動物は、死をどのように理解し、どのように反応するのでしょうか。
進化論的あるいは比較死生学とは「人間以外の動物の死と死にゆく過程の科学的研究」だと、京都大学の霊長類学者で人類学者のアンドレ・ゴンサルベス氏は言う。アリストテレス時代から、動物が死をどのように捉えているかについて理論化されてきたが、正式な研究は限られていると同氏は説明する。しかし、この新しい学問分野の出現により、それがゆっくりと変わり始めている。死生学に関する新たな観察は、私たち自身の行動がどこから来たのかを明らかにし、新たな疑問を喚起する。 手放したくないロンドン大学ユニバーシティ・カレッジの進化人類学准教授、アレシア・カーター氏は、ナミビアの同じフィールドサイトで何年もヒヒを研究してきた。彼女と同僚たちは、母ヒヒが死んだ子ヒヒの死体を運ぶ場面を何度も目撃してきた。当初、彼女はその行動に驚きはなかった。「ただ納得できる」と彼女は言うが、孤児になった死んだ子ヒヒが群れの他のメンバーに運ばれているのを観察するまでは。「その子と絆がなかった個体が、なぜその子を運ぶのか、よくわからなかった」。そこで彼女は、詳しく観察し始めた。 彼女は研究の中で、霊長類の間でこの「幼児の死体を運ぶ」行動がいかに一般的であるかを発見した。「このようなことが報告されていない種のグループはわずか数グループです」と彼女は言い、通常、その理由は明白な生理学的理由があると彼女は言う。例えば、キツネザルは子供を運ぶのにあまり適応していないが、生きている子供は自分でしがみつくのが上手いからだ。 カーター氏が共同執筆した2021年の研究によると、死体運びは類人猿や大型霊長類で最も多く見られ、乳児が非暴力的な死(病気など)で亡くなったときに最もよく見られる。死体運びの期間は種、乳児の年齢、その他の要因によって大きく異なるが、チンパンジーは100日以上も乳児を運び続ける場合もある。霊長類に限らない。乳児の死体運びは、ゾウ、ディンゴ、さらにはクジラ目動物でも記録されており、2018年には母親のシャチが死んだ子シャチを17日間支えて、約1,000マイルの海を渡った例がある。 動物がなぜこのような行動をとるのか、まだ正確にはわかっていませんが、いくつかの説があります。動物の親は自分の子供が死んでいることに気づいていないというのが一つの説です。しかし、キング氏とカーター氏はどちらも、それはあり得ない説明だと言います。死体を運ぶのは通常よりもかなりの労力を要することが多いため、この行動が通常のルーチンの延長ではないとキング氏は説明します。さらに、母親は「死体を生きている赤ちゃんとはまったく異なる扱い方」をするようで、「かなり早く」、とカーター氏は付け加えます。 カーター氏の見解では、幼児の死体を抱える行為は、母親と子どもの間に形成される非常に密接な絆の結果である可能性が高い。その愛着は、一度形成されると「断ち切るのは非常に難しい」とカーター氏は述べ、母親が死んだ子どもでさえも近くに置かざるを得ない生来の反応や認知的反応が働いているのかもしれない。キング氏の視点では、説明はさまざまだが、死体を抱える行為が大きな行動の変化をもたらす場合、それはおそらく何らかの馴染みのある感情に行き着くだろう。「悲しみは人間だけのものではありません。喜びや悲しみや恐怖も同様です」とキング氏は言う。死んだ子どもを抱える母親は、単に悲嘆しているだけかもしれない。「私たち人間は、考え、感じる他の種に囲まれています」。これは、動物とその生息地に対する扱い方を再考するきっかけになるはずだとキング氏は言う。 しかし、密接な絆も母親の悲しみも、群れが背負った孤児のヒヒを必ずしも説明するものではない。「観察研究で得られるのはここまでです」とカーター氏は言い、まだ答えが出ていない疑問がたくさんある。「私たちはこの分野のごく初期にいるのです」と彼女は付け加えた。 警備、世話、見張り動物が示す気遣いの表現は、死体を運ぶことだけではない。多くの種では、動物が長時間、身近な死体の近くに留まったり、動物学的な警戒のように死体を腐肉食動物から守ったりする様子が観察されている。「生き残ったグループのメンバーは、死体を守るためにあらゆる手段を講じることがある」とキング氏は言う。 キリンの母親が死んだ子のそばに何日も立っている様子が記録されている。アメリカ大陸全土に生息する豚のような荷役動物ペッカリーは、死んだ仲間の死体を10日間見舞い、守る様子がカメラに捉えられている。群れはコヨーテを追い払い、また時折、倒れた仲間の死体を鼻でなでたり押したりしていた。研究者らは、チンパンジーが死体の毛づくろいをしたり、歯を磨いたりする様子も目撃している。 アフリカゾウは「葬式」でよく知られている。これは、死者と関係のない個体も含め、多くの個体が長期間にわたって死体を訪れるという記録された事例である。ゴンサルベス氏は、ゾウが死者を埋葬することもあるが、「こうした事例は極めて稀にしか報告されていない」と述べ、ゾウの死に対する反応が、人間が行うレベルの正式な儀式の基準を満たしているかどうかに異議を唱えている。 哺乳類以外にも、特に長期にわたる絆を築く鳥類は、仲間の死体と一緒にいることが知られている。アヒルは死んだ仲間の死体の近く、あるいはその上で時間を過ごすことがあるという逸話もある。キング氏は、動物保護施設で救出された2羽のアヒルが「親友」で、何年も絆を保っていたという話をする。1羽が死んだとき、生き残ったアヒルは「死体に体をまとい」、その後は人付き合いをしなくなったという。 遺体の処分多くの種類の動物が親族の死に対して感情的(さらにはストレスホルモン)な反応を示すという証拠は豊富にあるが、すべての種に当てはまるわけではない。一部の動物では、死に対する反応ははるかに現実的である。 アリ、シロアリ、ハチなどの真社会性昆虫は、死体があるとすぐに行動を起こす。ほとんどの場合、巣や巣の仲間は、死体を別の場所に移すか、埋めるか、場合によっては共食いするかして、すぐに死体を群れから切り離す。ゴンサルベス氏によると、同じく母系コロニーで暮らすハダカデバネズミも同様の行動をとり、密閉された「ゴミ置き場」に死体を残すという。 こうしたケースでは、この「衛生」行為がコロニーの残りの部分を潜在的な病気から守るのに役立つと科学者たちは仮説を立てている。コロニーをきれいにするのは単に衛生上よいことだ。アリとシロアリの実験では、匂いが行動の主な原因であることがわかった。死んだ昆虫は生き残った昆虫を行動に駆り立てる化学物質を放出する。実際、これらの死臭を吹きかけられた生きた昆虫は死体と同じように扱われ、コロニーから取り除かれるとカーター氏は言う。 殺人的な好奇心さらに別の例では、死は一部の種にとって学習体験であるようだ。カケス、ワタリガラス、ワタリガラスを含むカラス科の鳥は警戒音を発し、仲間の鳥の死骸の周りに集まって「騒々しい集団」を作り、それが最長30分続くことが知られている。「葬式」と表現されることもあるが、研究者たちは、こうした交流の目的は哀悼というよりも情報収集と自己防衛にあると仮説を立てているとカーター氏は言う。鳥は捕食者を見つけて追い払おうとしているか、危険の源を突き止めて自分で避けようとしているのかもしれない。カラスに関するあるfMRI研究では、死んだ同種の鳥にさらされると、高次の意思決定に関連する脳領域の活動が活発になることが示された。 他の種も、死体と対面すると、必ずしも悲嘆するわけではないが、興味を示すようだ。あるカメラトラップ調査では、生きたウォンバットが何ヶ月もかけて死体を訪れて調べる様子が記録されている。 暴力的な反応もちろん、動物の行動の中には、人間にとって不快なものもある。多くの動物が死体と交尾する、つまり死体性愛や屍姦行為をすることが知られている。科学者たちは、カエル、トカゲ、カラス、ペンギン、アザラシ、イルカ、マカク、昆虫など、さまざまな動物のグループでこの種の反応を観察してきた。 動物が悲しんでいるのか、共食いを計画しているのか、あるいはその両方なのか、はっきりしないことがある。クマやオオカミのような捕食動物や腐肉食動物は、よく獲物の死骸を地中に埋める。肉は後で食べるために隠すのだ。ゴンサルベス氏によると、両種はそれぞれ別のケースで、死んだ子どもの死骸を埋めた記録もあるという。「肉食動物は同種の動物の死骸に遭遇すると、その匂いが埋める反応を引き起こすため、埋めることがある」と同氏は言う。しかし、一部の研究者は、この種の行動は哀悼に相当するのではないかと理論づけている。 混乱を増長させるのは、攻撃性が他の行動と混ざり合うこともあることだとカーターは言う。チンパンジーに関する追加調査では、チンパンジーが死んだ成体の雌を断続的に殴ったり、攻撃したり、毛づくろいをしたり、死体を調べたりした例が少なくとも 1 つ確認されている。霊長類がこのように支離滅裂な反応を示す理由の 1 つの仮説は、チンパンジーのように見えるが無生物のように振舞う何かの存在に、単に驚いたり、不安を感じたりするからだと彼女は説明する。おそらく「チンパンジーはただ怖がるだけ」だとカーターは示唆する。 説明不能で未知の動物の死に対する反応の多くは、そう簡単に分類、説明、または検出できるものではありません。そして多くの場合、私たち自身の思い込みが真の理解の妨げになることがあります。死んだ猫の周りを七面鳥が取り囲んでミームになったのを覚えていますか? これはある種の複雑な儀式のように見えましたが、おそらく、脅威と認識されたものが少し間違って、恐怖に駆られた反応だったのでしょう。 人間は動物の中に自分を重ね、根拠もなく擬人化する傾向がある。対照的に、科学者は人間があらゆる認知能力において並外れていると誤って想定することで、この習慣を過剰に修正する傾向があるとキング氏は言う。どちらのアプローチも正確ではない。しかし、偏見を持たずにさらに観察や研究を進めれば、永続的な死亡率の謎を解く手がかりが得られるかもしれない。 「答えの出ていない疑問がまだたくさん残っています」とゴンサルベス氏は言う。例えば、どの種が死とその永続性の概念を持っているのか(もしあるとすれば)はまだ明らかではないし、動物が多くの場合どのように死を認識するのかも明らかではない。「人間は死と生の境界線を非常にはっきりしたものとして認識することが多い」とゴンサルベス氏は言う。「他の動物にとっては、それはもっとぼやけて広い筆遣いのようなもので、眠っているとか負傷しているといった状態が不確かな中間地点で絡み合っているのかもしれません」 |
<<: ポラリス・ドーンの乗組員が歴史的な宇宙ミッションからの素晴らしい新画像を公開
推薦する
金の採掘方法を学んで、金採掘者の時代に入りましょう
初めて金の皿を手にしたとき、何が見つかるかはわかっていました。アラスカ州フェアバンクスのゴールド・ド...
ヨーロッパ人が実際に発見した土地はどこでしょうか? [インフォグラフィック]
1492 年、コロンブスは青い海を航海しました。そしてすぐに、何千年もの間多くの人々がすでに住んで...
億万長者のロバート・ビゲローは宇宙での人類の生活を実現できるか?
スカイウォーカー ウェイを下り、ワープ ドライブを左折します。格納庫のような施設がそこにあります。格...
私たちを月へ連れて行くのに役立った埋蔵金
人類史上最も貴重な品の一つが、ニーダーザクセン州の古い鉱山で埋もれていたのが発見されました。それは貴...
NASAの数十年ぶりの最大の月探査ミッション、アルテミス1号の打ち上げまでカウントダウン
中止、再開、議会公聴会での騒動、COVID-19、技術的な遅延、そしてさらなる技術的な遅延に直面した...
この代数学教師がなぜ生徒たちに授業で編み物をさせるのか
1 月のある雪の日、私は教室にいる大学生たちに、数学について考えるときに最初に思い浮かぶ言葉を尋ねま...
科学者は大気中の「輝き」が火星の温度を50度以上上昇させる可能性があると考えている
研究者たちは、火星の氷に覆われた不毛の荒野を溶かすための重要な味方はグリッター、より具体的には、文字...
これらの菌類は、パンプキンスパイスラテにもっとパンプキンを欲しがる
パンプキン スパイス ラテの季節が正式に到来しました。スターバックスのバリスタは、8 月末に秋メニュ...
古代ローマ人はコンクリートを作るのがはるかに上手だった
コンクリートの顕微鏡写真。CASH は、火山灰、石灰、海水が混ざったときに形成されるカルシウム・アル...
オオカミは待ち伏せ戦術を使って、油断しているビーバーを狩る
オオカミが徘徊するときは、通常、獲物が疲れ果てるまでシカやヘラジカなどの大型動物を追い詰める。しかし...
トウモロコシを果物、穀物、そして(ある種の)野菜にする奇妙な植物学
この投稿は更新されました。元々は 2019 年 9 月 24 日に公開されました。 「トマトは果物か...
スペースXは初の商業宇宙遊泳に挑戦する
今月、急成長を遂げる民間宇宙飛行の時代は大きな一歩を踏み出す。SpaceXは、2021年のInspi...
「おかしな暗黒物質」:宇宙膨張理論には何か問題がある
20世紀初頭から、宇宙が膨張していることはわかっていました。しかし、宇宙がどのくらいの速さで膨張して...
ラガーを発明したのは大きな間違いだった
ビールは人類に最も愛されている飲み物の一つであるだけでなく、人類最古の飲み物の一つでもあります。最近...
発がん物質について、実際にどの程度心配すべきでしょうか?
過去数年のニュース記事では、太陽光の紫外線から焦げたトーストまで、あらゆるものが潜在的な発がん性...