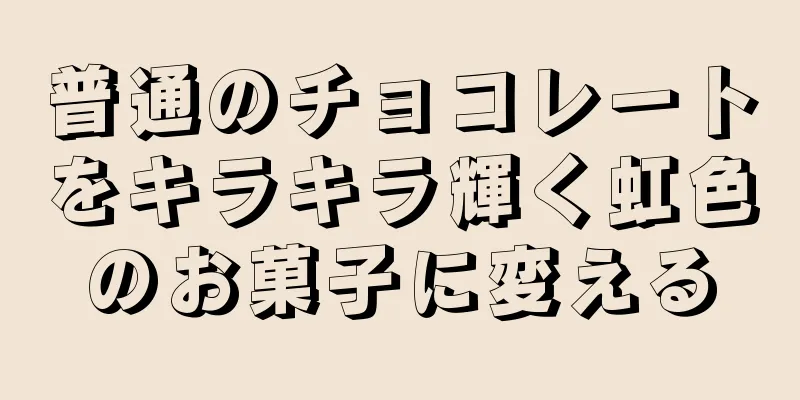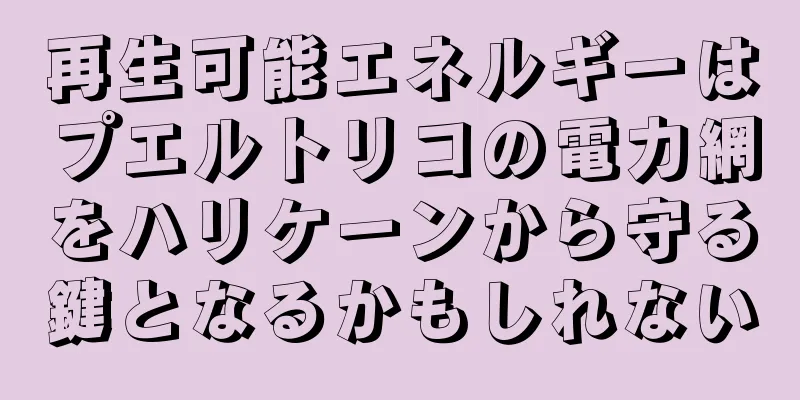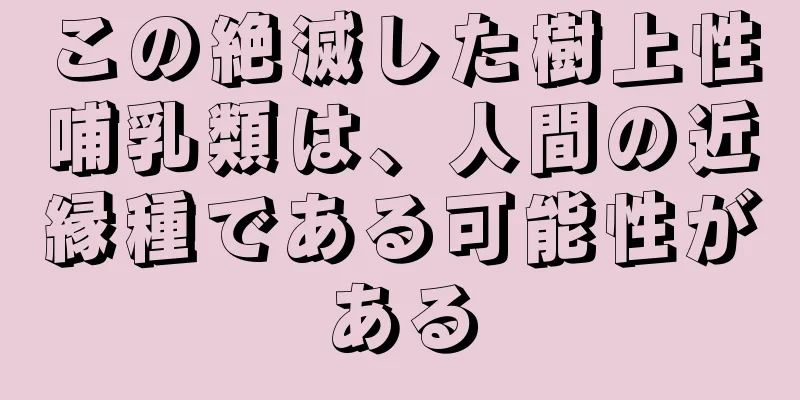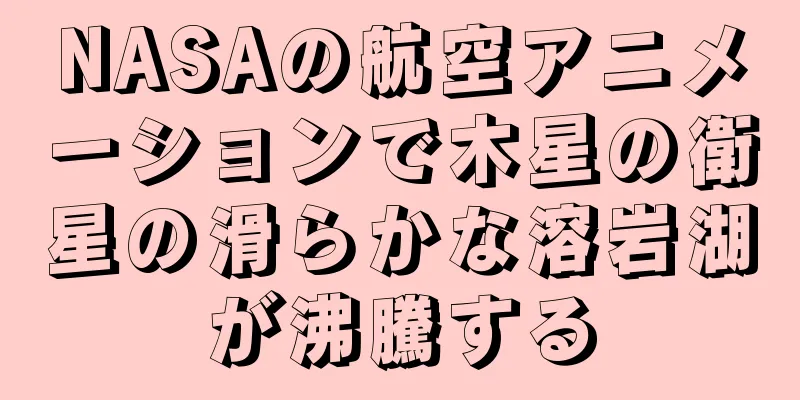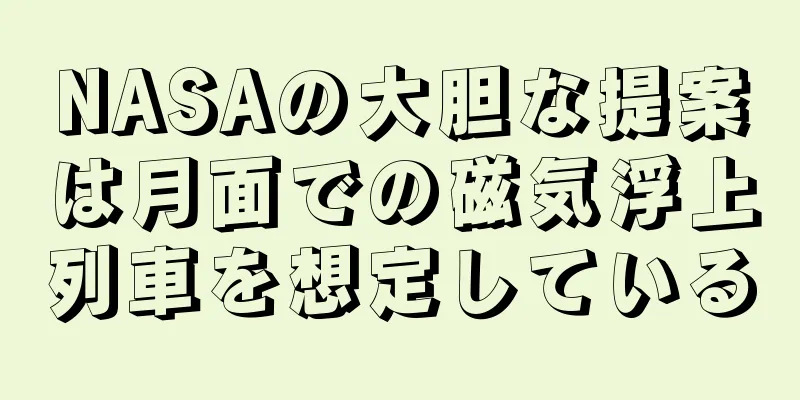人間は本当に犬を家畜化したのでしょうか? 犬の歴史はあなたが思っている以上に謎に満ちています。
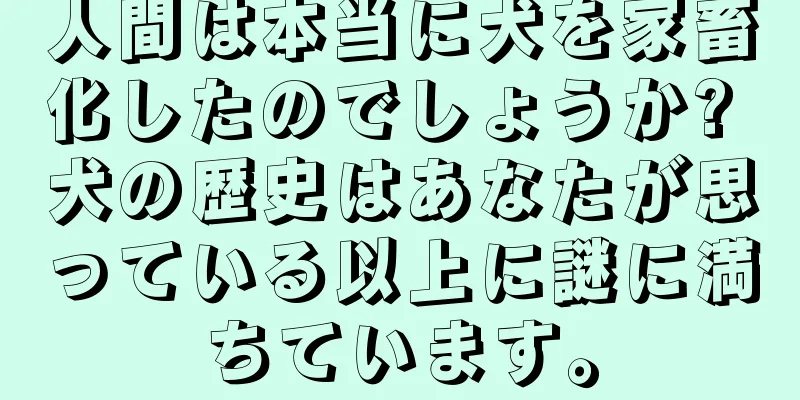
|
チェビーという名前の白黒のボストンテリアは、タキシードを着たアザラシのようにスマートで粋で、防音の実験室にさっそうと歩いて入ってくる。彼の陽気な自信は、研究チームが彼を一連の心理学実験にかけるとすぐに消え去る。その実験は彼を怖がらせ、落胆させ、最終的には困惑させる。かわいそうなチェビーは、科学のためにガスライティングを受けようとしている。 この小柄なテリアは、ハーバード大学の進化神経科学者エリン・ヘクトが立ち上げた野心的なプロジェクトの初日にボランティア第 1 号として参加した。このプロジェクトは、犬が何をするのか、なぜそうするのかという基本的な疑問に答えるためだ。彼女は、犬がどれだけ簡単に友達を作れるか、どれだけ行儀が良いか、掃除機に対してどう感じているかなど、あらゆる犬種の何百匹もの心理と行動に関するデータを何年もかけて収集する予定だ。4 台のビデオカメラが、実験者の正確に台本化された動作に対するシェビーの反応を記録している。隣の応接室では、ヘクトのチームの残りのメンバーがマジックミラー越しにその様子を見ている。 ハーバード大学のハンナ・マクイスティオンさんは、まず犬を撫でたり撫でたりした後、シェビーにおやつを数個与え、次のおやつをガラス瓶の下に置いた。シェビーはそれを熱心に嗅ぎ、それから彼女に懇願するように見つめ、首を前後に傾け、最大限にかわいくする。これは典型的な行動だとヘクトさんは説明する。困難な状況に直面した犬は、すぐに人間に助けを求める。20秒後、マクイスティオンさんはシェビーのために瓶を持ち上げる。シェビーはおやつをむさぼり食う。 簡単なテストを数回行った後、彼女はチェビーを大きな金網の檻の中に入れ、部屋に一人残しました。彼はそわそわして、小さくすすり泣きました。2 番目の実験者、ステイシー ジョーがすぐに入ってきましたが、彼女は背を向け、しばらくの間壁の方を向いていました。その間、チェビーはじっと彼女の背中を見つめていました。彼女は目を合わせることも話すこともなく、彼の檻に近づき、ドアのちょうど 30 センチ前に座り、彼の胸に目を向けました。チェビーはじっと立ち、耳を立て、わずかに震えていました。非科学的に言えば、この犬は完全に奇妙に感じています。鏡の反対側から見ると、その光景は、世界で最も気まずいデートのように、苦痛でもあり、滑稽でもあります。勇敢にも、ジョーは真顔を保っています。 これらの検査データとDNAサンプルは、野生から飼い慣らされた犬に何が変わったのかという新たなヒントをヘクト氏に与えることになる。生物学的には、犬はほとんどがオオカミで、厳密に言えば亜種Canis lupus familiarisだが、根本的に祖先とは異なっている。野生動物を飼い慣らすために手で育てれば、その個体は穏やかで温厚になるかもしれない。しかし、家畜化は別の話だ。犬や私たちと暮らす他の動物にとって、寛容と信頼は遺伝子と脳に刻み込まれている。 ヘクトの研究は、強い環境圧力の下で神経物質がどのように進化するかというより広い主題、つまり、この場合は、他の種と共に生き、依存し、愛するという非常に特殊な状況への洞察を得るための方法である。「私は犬に興味があります。犬自体に興味があるだけでなく、人間について学べることにも興味があります」と彼女は言う。「しかし、より一般的には、犬は脳がどのように進化するかという基本的なプロセスを理解するための素晴らしい方法です。」 彼女は、これらの毛玉のような動物がどのようにして私たちの顔をなめ、尻尾を振って一番のファンになったのかを解明しようとしている研究者たちの一人です。私たちは、人間が家畜化の物語を書いたと考えたいものです。銀河系の頭脳を持つ狩猟採集民がオオカミの子犬を誘拐し、獲物を嗅ぎ分けるパートナー、番犬、仲間として新しい種を作り上げたのです。しかし、ますます多くの研究者が、この物語の原作者は犬であると考えるようになっています。はるか昔、オオカミが私たちの運命と運命を結びつけ、私たち二人の運命を永遠に絡ませる特別な恋愛関係を築きました。 考古学は、犬がいつどこで家畜化されたか(現在の考えでは、少なくとも 15,000 年前にヨーロッパ、アジア、またはその両方で起こった)を突き止めるのに役立つが、骨は、この物語がどのように、なぜ起こったかについてはほとんど何も語っていない。キツネやオオカミなどの他のイヌ科動物を研究し、犬の遺伝子、行動、脳(優しく、友好的で、信頼感がある脳)を分析することで、研究者たちは、大きな悪いオオカミがどのようにして愛らしい小さな犬になったかについて新しい考えを発展させている。彼らの社会的な知性が彼らを特別なものにしていると主張する人もいれば、彼らの献身、つまり人間に対する深い魂の渇望を指摘する人もいる。 最初に家畜化された種である犬は、私たち人間を含む他の哺乳類が家畜化された過程のモデルでもあります。科学者たちは、犬の遺伝子と精神の中に、人間自身の並外れた寛容さに関するヒントを見出しています。人類が単なる霊長類から世界征服の原人になるまでの道のりの大半において、犬は私たちのすぐそばにいました。犬は私たちにとって身近な存在であり、私たちの反響であり、私たちの影です。そして今、犬たちの目をもっとよく見ると、私たち自身の新たな姿を垣間見ることができます。 2011年のある夜、ヘクトさんと彼女のミニチュア・オーストラリアン・シェパードのレフティがソファでテレビを見ていると、伝説のベリャーエフ・ギツネに関する番組が流れた。ドミトリー・ベリャーエフは1950年代初頭のソ連の遺伝学者で、当時はモスクワが帝国主義的な西側諸国の産物として遺伝子研究を抑圧していた。 ベリャーエフは、自分が選んだ分野を公然と研究することができなかったが、独創的な計画を思いついた。毛皮のために飼育されたキツネを実験的に飼いならすのだ。人間が飼う動物は繁殖頻度が高いため、公式にはソ連の毛皮生産を加速させることになる。しかし、このプロジェクトには科学的な要素も盛り込まれていた。彼の理論は、飼い慣らすために飼育するだけで、現在「家畜化症候群」と呼ばれる現象が現れるというものだった。幼稚な行動、腹部や顔の白い斑点、垂れ耳、短い鼻、小さな歯などの身体的変化などだ。 研究は1959年にシベリアで本格的に始まりました。ベリャエフのパートナーは、同時にあまり怖がらず、攻撃性も低い動物(これらの特徴は通常は連動しています)を選択し、交配しました。わずか4世代後の1963年、共同研究者のリュドミラ・トゥルトがキツネの檻に近づくと、子ギツネの1匹が彼女に向かって尻尾を振りました。1965年までには、数匹の若いキツネが子犬のように背中を転がして鳴き声をあげて注目を求めていました。研究者たちはまた、無作為に交配した対照群の動物を飼育し、その後、極度に怖がりで闘争心の強いキツネの系統も飼育しました。この画期的な研究は今日まで続いています。 ヘクトはこの歴史をすでに知っていた。しかし、番組を見て、キツネの脳を分析する人は誰もいなかったことに気づいた。通常、人間は気質、大きさ、毛色など、多くの特徴を身につけるためにヤギやヒツジなどの家畜を飼育しており、これらはすべて、意図せずして心に痕跡を残す可能性がある。しかし、飼い慣らされたキツネの頭と普通のキツネの頭の違いは、行動の選択だけによるものである可能性があり、ベリャーエフとトルートが行ったのと同じだ。それらは灯台のように目立ち、どの回路または新しい神経化学が、身をすくめてうなり声を上げる小さな雌キツネをかわい子ちゃんに変えたのかを正確に明らかにするだろう。そして、進化がどのように心を作り変えることができるかをより深く理解するための道を示すだろう。 「一方では、脳がどのように進化するかという基本的な疑問があります」とヘクト氏は言う。「そして、より具体的な疑問は、家畜化の神経的相関は何かということです。驚くべきことに、私たちはそれを知りません。」少なくとも今のところは。 彼女が発見したものは、いくつかの新たな理論への洞察も提供する可能性がある。2005年に人類学者ブライアン・ヘアと心理学者マイケル・トマセロが提唱した理論では、昔、非常に勇敢なオオカミが人間の周りをうろついて食べ物をあさり、臆病でない種が生まれたと提唱している。恐怖にとらわれなくなったこれらの原始的な犬は、既存の社会スキルを再利用して人間を理解し、コミュニケーションをとることができた。彼らは自ら家畜化した。それが犬の本質だとヘアとトマセロは主張している。つまり、恐怖心が減ることで高度な社会的認知が可能になり、人間の心を読む不思議な能力が身につくのだ。彼らはこの考えを「家畜化仮説」と呼んだ。 その証拠は、子犬は教えなくても私たちを理解するということです。たとえば、チンパンジーは指さしのジェスチャーに従うのに苦労しますが、ほとんどの雑種犬はすぐに理解します。シェビーがしたこと、つまり問題を解決するためにマクイストンに頼ったことは、別の例です。彼は本能的に助けを求める方法を知っていたのです。 ヘクトはキツネの脳の溝と脳柄を見れば、この説や他の説が正しいかどうかの兆候がわかるかもしれない。彼女はトゥルットに電子メールを送り、トゥルットはロシアキツネの最近の世代から数十の標本を送ってくれた。そして、MRI を使ってキツネの脳のさまざまな構造の相対的な大きさと形を測定した。 ヘクトは、感情や社会的行動に関わる大脳辺縁系と前頭前野の部分に変化が見られた。これらのデータは「家畜化仮説」を裏付ける可能性があるが、他の競合する考えを排除するものでもない。この最初の発見は、異なると予想される脳の領域が実際に異なることをほぼ裏付けている。そこで、より詳細な画像を得るために、ハーバード大学のポスドク、クリスティーナ・ロジャース・フラタリーは、キツネの脳を組織のように薄いスライスに削り、神経化学を明らかにする染料で染色することで、分析に別の次元を追加している。彼女は、神経ホルモンのバソプレシンを作るニューロンの経路と、セロトニンサブシステムに注目しており、どちらも攻撃性に関連している。彼女はまた、社会的結びつきを促進するオキシトシンを作る細胞も調査している。社会的結びつきに関わる回路の強化や、暴力的な攻撃を引き起こすシステムの抑制など、飼いならされた行動につながる可能性のある神経の修正は数多くある。フラタリーの調査と脳スキャン、そして3人目の協力者であるイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の遺伝学者アンナ・クケコバの遺伝学に関する洞察を組み合わせれば、研究チームは「従順さに関する大統一脳理論」、あるいは少なくともその神経回路図を特定できるかもしれない。 シェビーが彼の指示に答えるとき、彼は自分自身だけでなく、彼の犬種も表している。ピットブル、ペキニーズ、アイリッシュウルフハウンドにはそれぞれ異なる性格や能力があると誰もが感じているが、ヘクト氏はそれらの違いを突き止めたいと考えている。これは、選択圧(この場合は、犬舎クラブによる伝播)が脳をどのように形成するかを探るもう1つの方法だ。最近の論文で、ヘクト氏は33犬種のMRIスキャンを分析し、例えばワイマラナーの頭には視覚処理のための余分な領域があり、バセットハウンドの頭は匂いを分析するようにできていることを発見した。 同じ論文で、ヘクトはボストンテリアの脳にも注目した。その脳には社会活動に関連するネットワークが詰まっている。シェビーも例外ではないようだ。検査がすべて終了し、DNAサンプルが採取されると、シェビーは待合室に飛び込んできて、一人一人に挨拶するために駆け回る。至福と喜びの小さな旋風だ。 2015年の研究結果によると、この小さな犬が人間の目をじっと見つめると、犬の脳内(そして私たち一人ひとりの頭の中でも)でオキシトシンが少量放出される可能性があるという。このホルモンは絆を深める作用があり、トラウマを経験した人々にとって犬がセラピーや感情サポートの動物として非常に優れているのはそのためかもしれない。 こうした友達作りのエクスタシーの渦は、認知よりも感情に焦点を当てたライバルの起源理論を刺激した。アリゾナ州立大学の行動科学者クライヴ・ウィンの言葉を借りれば、「頭ではなく心」だ。フロリダ大学のニコール・ドーリーとオレゴン州立大学のモニーク・ウデルの共同研究者とともに、ウィンは犬のアイデンティティの本質は感情的なつながり、つまり科学では珍しい言葉で言えば愛と関係があると提唱している。「ある意味、それは明白です」とウィンは言う。「犬は驚くほど愛情深いのです。ただ、調査対象になるほど深刻に聞こえないという理由もあって、避けられてきただけなのです」 研究者たちは2008年に「家畜化仮説」のさらなる証拠を確立しようとしたときに、偶然この研究にたどり着いた。しかし、犬とオオカミを直接比較した研究では、まったく逆の結果が出た。インディアナ州の研究機関でよく社会化されたオオカミは人間の指さし動作に簡単に従ったが、人間とほとんど接触のない保護施設の犬の中には従わないものもあった。(その後の研究で、コヨーテや、人の手で育てられたコウモリも同じように従うことができることがわかった。) もう一つの驚きは、それぞれのイヌ科動物が身近な人のそばにいる時間を計測する簡単なテストから生まれた。イヌは近くにくっつくが、オオカミは、たとえ友好的に育てられたものであっても、近くにくっつかない。イヌは、他の種のメンバーとさえも絆を築こうとする独特の衝動を持っていると研究者は考えた。世界中の約7億5000万匹の野良「村の犬」を含め、すべての子犬がその能力を持って生まれる。ちなみに、種間の絆を形成する能力は、家畜の品種が羊やアヒルを守るために非常に用心深くなれる理由も説明している。 最近では、プリンストン大学の進化生物学者ブリジット・フォンホルト氏が、この愛情の根源と思われるものを発見した。彼女とチームは、犬の DNA で、染色体 6 に進化圧のマーカーを発見した。人間では、同等の突然変異がウィリアムズ・ボイレン症候群を引き起こす。これは、無差別な友好性、つまり社交性過剰につながる発達障害である。「私は、非常にポジティブで愛情深い形で、犬は犬版のこの症候群を持っているのではないかと考えています」と彼女は言う。この場合も、変化は当初、人間が意図的に行ったものではなく、犬に生じたものである。 遺伝子をいくつか変えるだけで、イヌ科の動物や人間がみんなの親友に変身できるかどうかは不明だが、理由は不明だが、この傾向は、コフやラブラドール・レトリバーなど一部の犬で他の犬よりも強い。ヘクトのテストの一つ、「共感課題」では、実験者のマクイスティオンがハンマーで親指を叩き潰すふりをして、痛みを訴える。実験対象動物の中には、実験者の膝に飛び乗って、模造の傷をなめるものもいる。シェビーは実験者をほとんど無視している。 それでも、同じ環境で育てられたさまざまな種類のイヌ科動物の研究は、過度の社交性も「家畜化仮説」のような社会認知理論もすべての疑問に答えるものではないことを示唆している。10年前から、ストックホルム大学とウィーン獣医大学のオオカミ科学センターのチームは、研究室でイヌとオオカミの群れを育て始めた。生後数か月間、どちらの子犬も1日24時間人間と一緒にいる。その後、動物は群れで生活し、人間と広範囲に交流する。 これらの実験は、犬が単に社交スキルに優れたオオカミではないことを示している。第一に、手で育てられたオオカミは非常に愛想がよく、飼い主に喜んで挨拶し、リードをつけて散歩に出かける。2020年、ストックホルムのチームは驚いたことに、子犬のうち数匹が犬と同じように「取ってこい」というしぐさを直感的に理解していることに気づいた。 実際、ウルフサイエンスセンターの研究では、状況によってはこれらの野生動物の方が犬よりも寛容であることがわかっています。分け合う食べ物を与えられると、犬は互いに距離を保ちます。オオカミは最初は口論したりうなり声を上げたりしますが、その後は並んで平和に食べます。ある研究では、オオカミまたは犬のペアが肉片を取り出すために協力しなければなりませんでした。オオカミは効果的に協力しますが、犬は「ひどく下手」だったと研究者のサラ・マーシャル・ペシーニは言います。彼女がオオカミと人間、犬と人間の協力パートナーをテストしたとき、パターンはより明確になりました。オオカミはリードを取ることを恐れませんが、犬は後ろに下がって人間が最初に動くのを待ちます。 これらの予想外の発見から、マーシャル・ペシーニは自己家畜化のさらに3番目の理論にたどり着いた。おそらく、この変化は新しい社交スキルや愛情表現ではなく、むしろ新しい対立管理戦略だったのだ。人間は、おそらく、大胆で自己主張の強いオオカミを脅威として殺しただろう。しかし、キャンプの周りをこっそり歩き回り、施しを期待する従順で回避的な原始的な犬には我慢していたかもしれない。(攻撃的な品種は、おそらく最近の現象で、ほぼすべての現代の品種を生み出した18世紀と19世紀の犬愛好家の結果である。) 彼女のグループは、村の犬を観察して、犬の社会構造と人間に対する犬の反応について理解を深めようとしている。私たちのペットと比べると、これらの放し飼いの動物は、はるか昔の祖先である初期の犬にかなり似ていると思われる。友好的な犬もいれば、内気な犬もおり、生き残るために頼りにしている毛のない類人猿と、不安で相反する関係にある犬たちだ。 この研究の周辺には、キャンプファイヤーの向こうに忍び寄るオオカミのように、私たちも自らを家畜化したのではないかという考えが潜んでいる。それが、ヘクトが飼い慣らしの特徴を見つけたいと考えている理由の1つだ。もしそれができれば、飼い猫と野生猫の脳を比較し、また人間の灰白質と類人猿を比較して、同じパターンを探すことができる。人類学者ヘアによる人類の起源に関するこの説明「最も友好的なものが生き残った」は、犬と同じように、私たちもはるか昔の過去に互いをより信頼し、寛容になり、それが今度はコミュニケーションにおける超能力の開発を可能にしたと仮定している。言語はその明らかな例の1つだ。 人間の自己家畜化という考えは、少なくともダーウィンの時代から議論されてきたが、今日では実際に証拠があると、ハーバード大学人類進化生物学部の霊長類学者リチャード・ランガムは指摘する。人間は(霊長類としては)異例なほど他人に寛容で、思春期が長いことに加え、家畜化症候群に関連する身体的特徴のいくつかを示している。ヒト科の親戚と比べると、人間の顔は短く、歯は小さい。2014年には、ランガムと共同研究者らは、胚発生中に体の多くの部分を形成する神経堤細胞に生物学的メカニズムが存在する可能性を提唱した。現代では信じがたいように思えるかもしれないが、その意味するところは、人間という種が互いに平和的に付き合うように進化したということだ。 2019年12月、ヨーロッパの研究グループは、ウィリアムズ・ボイレン領域にある遺伝子BAZ1Bが、そのような細胞を誘導することで顔の形に影響を与えることを発見した。これは、人間の自己家畜化の物語の一部を説明できるかもしれないとランガム氏は言う。 ヘクトの研究室に戻ると、コーダという新しいボランティアが彼のテストを行っている。(偶然にも、彼もボストンテリアだ。)ある課題では、マクイスティオンは床におやつを置き、「ダメ! 取らないで!」と言ってから目を閉じる。犬は目を閉じることが何を意味するかを知っているので、この時点でほとんどの犬がおやつを奪い取る。コーダは違う。飼い主が指摘するように、彼はいつもとても良い子だ。彼はこっそりおやつを見て、唇をなめ、それから憂鬱そうに空を見つめ、犬としての宿命のように、待ち、先延ばしにし、争いを避けている。 マジックミラーの向こう側では、人間たちがこのドラマにすっかり夢中になっている。「いい子だね」と誰かが言う。マクイスティオンがようやくおやつを食べる許可を与えた後も、彼はまだそこに立っていて、彼女を悲しそうに見つめている。待合室で合唱が沸き起こる。「さあ、コーダ、受け取って!」 私たちは皆、彼の欲望を見て、彼の抑制を感じる。いったい誰が、誰の心を読むように進化したのか、考えさせられるほどだ。 犬を見ることは、たとえマジックミラー越しであっても、私たち自身の種を見ることでもある。調和して生きるために、お互いを理解するために、恐怖と攻撃性を愛と忠誠心で置き換えるために何が必要なのか。おそらく、だからこそ犬は完全に楽しい存在なのだ。犬は、私たちのより良いバージョンを思い出させてくれる生きた存在なのだ。午後の心理的な刺激が終わると、コーダはご褒美を取って体を振る。飼い主が部屋に入ってくると、彼は彼女の膝の上に飛び乗って幸せそうにハアハアと息を切らし、飼い主がまっすぐに見つめる目をじっと見つめる。 このストーリーは、 Popular Scienceの2020年春のOrigins号に掲載されています。 |
<<: スウェーデン王は本当に致命的な科学実験でコーヒーを禁止しようとしたのでしょうか?
推薦する
今週末に私たち全員が受け取る無料ボーナスセカンドをどうするか
地球の自転は私たちの計算と完全には一致しないため、一貫性を保つために調整する必要があります。今週末に...
ノロウイルスが全米で急増
不快で伝染性の胃腸炎ウイルスであるノロウイルスが米国で蔓延しており、先週はデトロイト郊外の学校が数日...
この遠く離れた海王星のような惑星は、実際には存在しないはずである
「禁断の惑星」について知る時が来ました。1956 年の SF 映画の古典ではありません。私が話してい...
血を飲んでも大丈夫ですか?
内なるモービウスやドラキュラを呼び起こすにせよ、ゴブレット一杯の血を飲み干すという行為は、現実世界で...
難破船ハンターがスペリオル湖で第二次世界大戦時代の船を発見
難破船ハンターのチームが、1940年にスペリオル湖の氷の海に沈んだ商船の残骸を発見した。全長244フ...
NASAは月面用担架の設計にあなたの協力を必要としています
NASA のアルテミス III ミッションは、ほぼ 55 年ぶりに人類を月面へ帰還させる。しかし、そ...
ブルームバーグ市長は海面上昇に対してニューヨーク市を強化する計画
本日、ニューヨーク市のブルームバーグ市長は、気候変動の将来の影響に備え、市を強化するための200億ド...
地球の水の起源は大きな謎だが、パズルのもう1つのピースが見つかったかもしれない
もし地球に水がなかったら、生命は存在せず、宇宙には湿ったミームがほとんど存在しないことになる。しかし...
母から受け継いだもの:母に感謝すべき意外なこと4つ
ニンニク、タマネギ、その他の強い風味を好む赤ちゃんは子宮の中にいる間に味覚と嗅覚を学び、羊水を口いっ...
世界最大の実験用トカマク型核融合炉が稼働中
日本と欧州連合は、世界最大の実験核融合施設の試験を正式に開始した。東京から北に約85マイルに位置する...
スペースXのスターシップが飛行し、腹ばいになって炎上
スペースX社のロケット科学者にとって、火星は昨日、さらに数マイル近づいた。同社の主力宇宙船は新たな高...
科学者たちはこれらのクラゲ銀河の中心に驚くべきものを発見した
私たちの銀河である天の川は、誰もが知っていて愛している、古典的で気楽な風車の形で宇宙を進んでいく渦巻...
火星地震は火星生命の鍵となるかもしれない
火星の地震は、火星の地表下で極小の微生物が生き延びるのに役立った可能性がある。地球上の岩石で地震活動...
銀河の中心にある超大質量ブラックホールを眺める
天文学者たちは、天の川銀河の中心にある超大質量ブラックホール、いて座A*の画像を初めて公開した。この...
ファンは『スター・ウォーズ』の新予告編に驚愕
ムスタファーでオビ=ワンと運命的に戦った後のダース・ベイダーと同じように、スター・ウォーズのファンは...