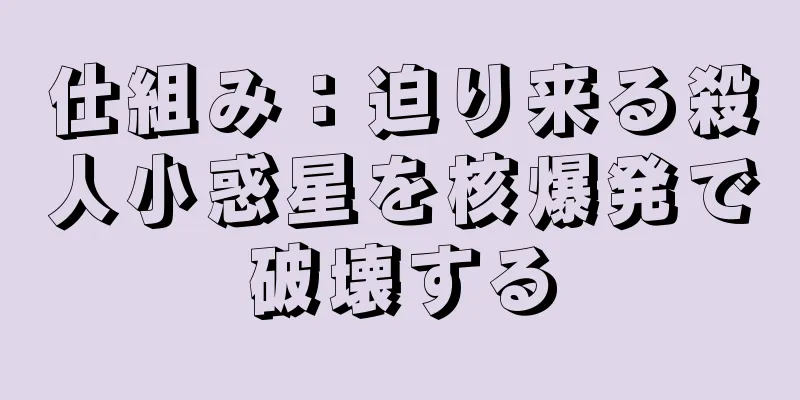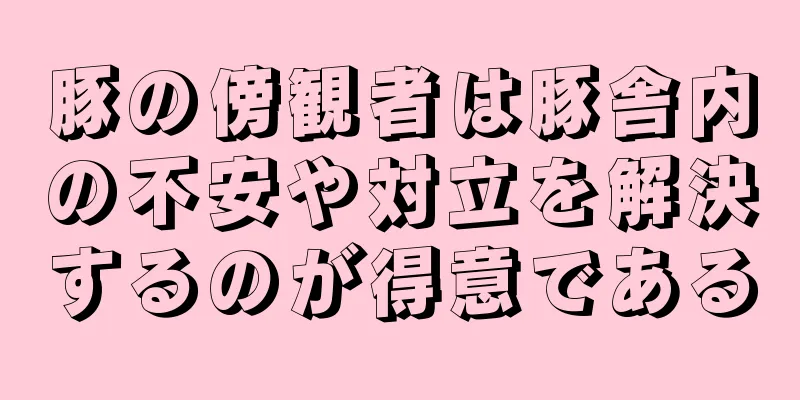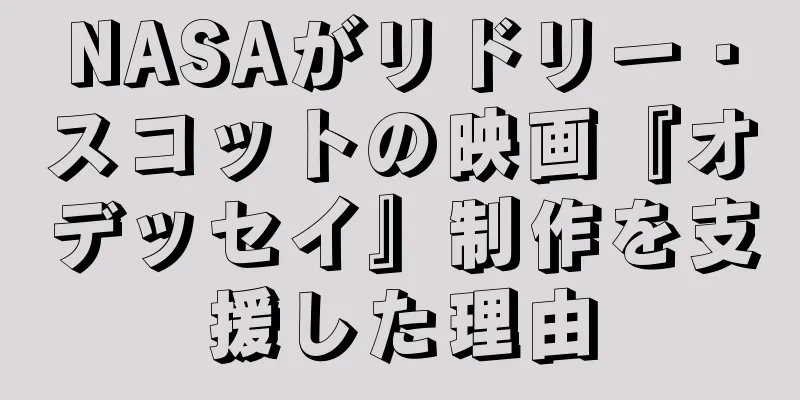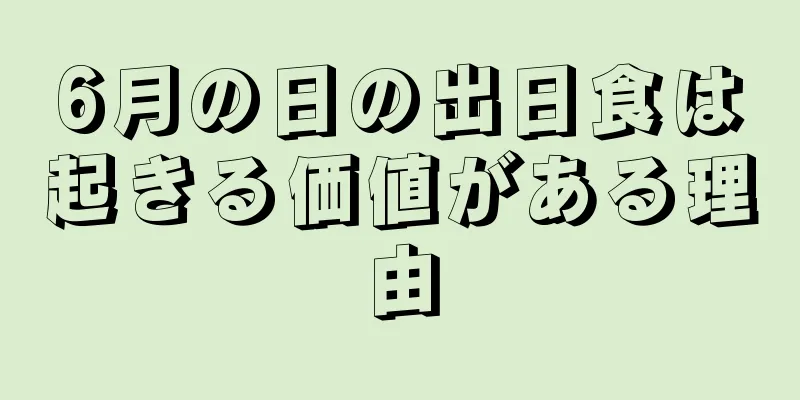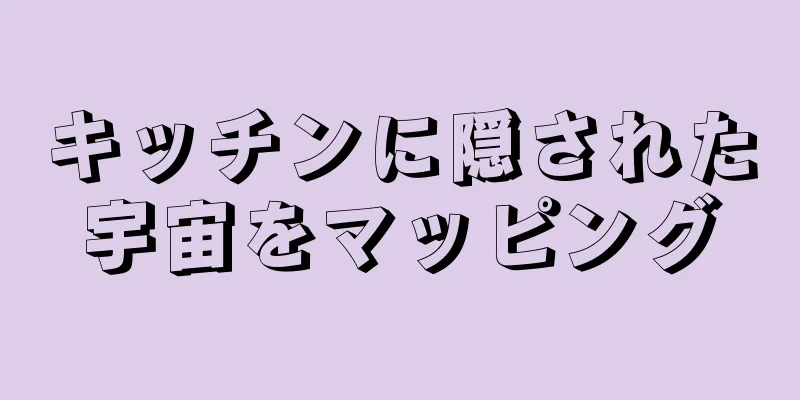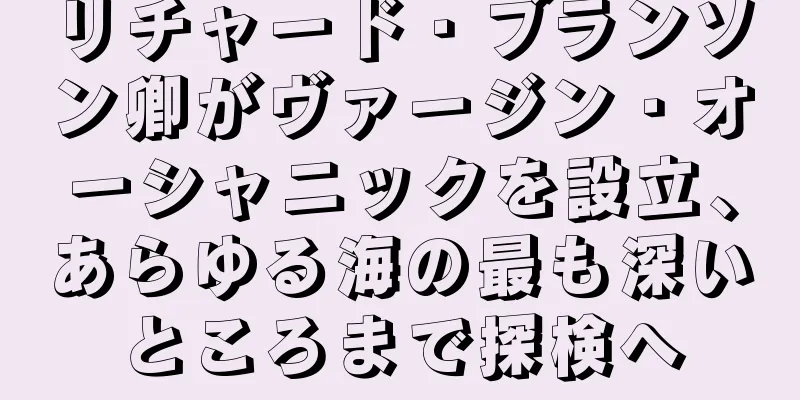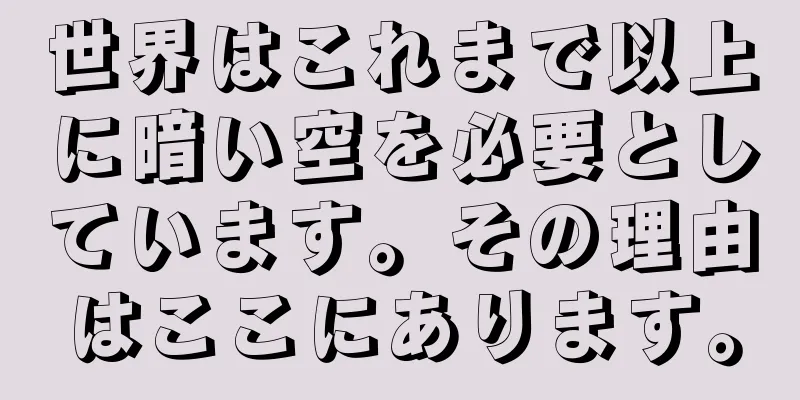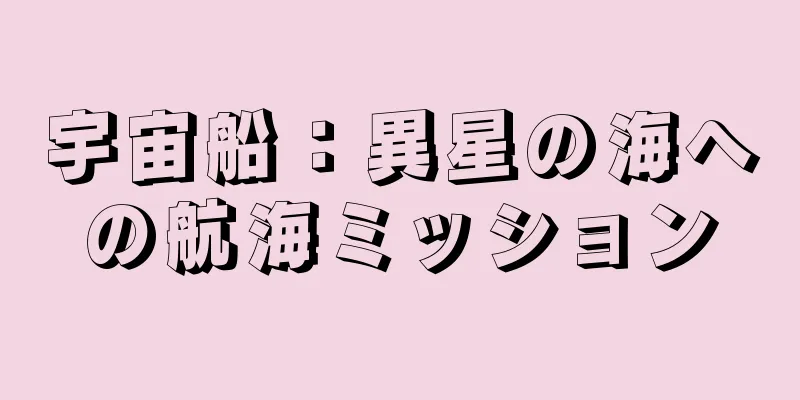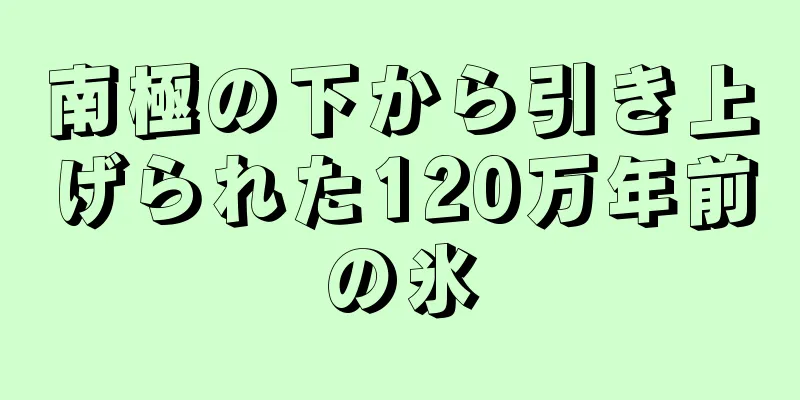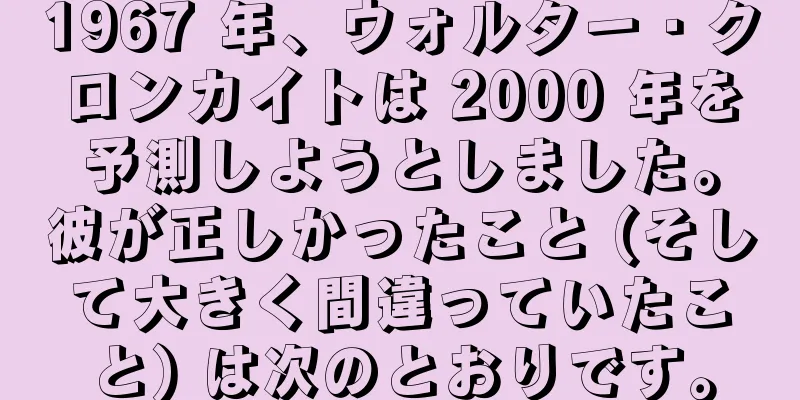この1億2000万年前の鳥は舌を突き出すことができた
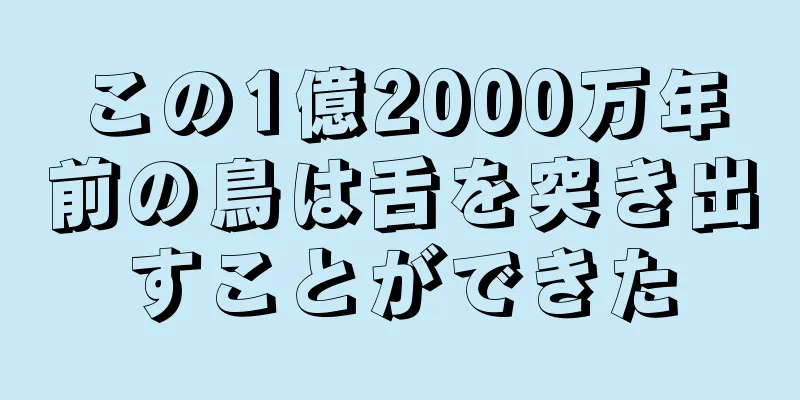
|
約1億2千万年前、現在の中国北東部に、舌を突き出す珍しい能力を持っていたと思われる鳥が生息していた。 科学者らは、12月1日付けの解剖学ジャーナルで、この古代の鳥のほぼ完全な骨格について説明し、ブレビロストルアビス・マクロヒオイデウスと名付けた。この化石の極端に長い舌付着骨、つまり舌骨は、この鳥が口から舌を突き出すことができたことを示唆している。これは、現代の鳥が届きにくい食べ物をつかむために行うのとよく似ている。 メリーランド州フレデリックのフッド大学の生物学助教授で、この研究には関わっていないロバート・カンビック氏は、ブレビロストルアヴィスは、現代の鳥類とその絶滅した近縁種がともに、食料を確保するためにさまざまな方法を発達させてきたことを浮き彫りにしていると話す。 「鳥は進化の過程で、早い段階でさまざまな種類の摂食適応と戦略を試してきました」と彼は言う。「この多様な習慣と摂食方法は、現生の鳥に特有のものではなく、実は鳥類の系統全体を代表しているように見えるというのは、本当に素晴らしいことです。」 人間の場合、U 字型の舌骨は舌の根元、喉頭のすぐ上にあります。「この骨は他の骨に付着しておらず、さまざまな方向から付着する筋肉によって浮いています」とカンビック氏は言います。「舌の筋肉の中には、特に舌を突き出したり引っ込めたりする場合に、このアンカー ポイントを必要とするものがあります。」 鳥類は一般に、人間のような筋肉質で機敏な舌を持っていないが、肉質の舌を持つ種も少数ながらおり、くちばしで果物や種子の皮をむくのに役立つ。また、いくつかの科では、舌骨器官とくちばしの一部が長くなっており、舌を突き出せるようになっている。ハチドリは機敏な舌を使って花の奥深くから蜜を吸い上げ、キツツキは舌を伸ばして木から昆虫や樹液を吸い取る。 「キツツキは極端な例です」と、北京の中国科学院の古生物学者で、今回の研究結果の共著者でもある李志恒氏は電子メールで述べた。「彼らの舌は非常に長く、頭頂部に巻きつき、鼻孔の1つにも入り込むほどです。」 新たに報告されたブレビロストルアビスは、エナンティオルニス類と呼ばれる多様な初期鳥類のグループに属し、現生種は存在しないが、白亜紀には世界中で優勢だった鳥類である。標本は、白亜紀前期の中国遼寧省の岩石の中に保存された状態で発見された。ブレビロストルアビスはムクドリほどの大きさで、長い爪と足指の骨の比率から、この生物が樹上生活者であったことがうかがえる。 研究者らがブレビロストルアビスの化石を調べたところ、他の現生鳥類や絶滅鳥類には見られない奇妙な特徴の組み合わせも特定した。 現代の鳥類では、舌骨は軟骨と、棒状の鰓鰓骨と上鰓骨を含むいくつかの骨で構成されています。舌を突き出すことができる現代の鳥類は、特に長い上鰓骨と細長い嘴を持っています。初期の鳥類にはこれらの骨はありませんでした。Brevirostruavis では、曲がった鰓鰓骨が頭蓋骨のほぼ全長にわたっています。 さらに不可解なことに、ブレビロストルアヴィスは短く尖った吻部を持ち、その吻部には釘状の歯が並んでいた。この非常に長い舌骨器官と短い吻部というユニークな組み合わせには、いくつかの説明が考えられるとカンビック氏は言う。 「舌をできるだけ遠くに出すのではなく、長い筋肉の付着部は、食べ物を口の中や口の近くで動かすのに本当に必要な筋肉質の舌にとっても良いかもしれません」と彼は推測する。 もう一つの可能性は、ブレビロストルアヴィスは確かにその印象的な舌骨を使って舌を突き出していたが、何らかの進化上の制約により、この鳥はくちばしのような鼻先を長くすることができなかったというものだ。「そのため、この鳥は舌が長いのに、それを支えるくちばしがないのです」とカンビック氏は言う。「この鳥はシステムの 1 つの部分しか持っていませんが、現生鳥は 2 つの部分を持っていて、それらが連携して機能する可能性があります」 [関連: これらの古代の鳥類にとって岩石はメニューだったのか?] ブレビロストルアビスは他の鳥が手に入らない食料源を利用できた可能性があるが、標本の最後の食事の残骸が保存されていないため、何を食べたのかはっきりしない。それでも、ブレビロストルアビスが舌を使って樹皮に隠れた昆虫を探したり、先史時代の植物の生殖球果にある蜜のような液体や種子に手を伸ばしたりしていた可能性はあるとリー氏は言う。 研究チームはブレビロストルアヴィスとその近縁種との進化的関係も分析した。ブレビロストルアヴィスはエナンティオルニス類のどの主要グループにも当てはまらないことがわかり、細長い舌骨器官が鳥類の系統樹全体で複数回にわたって独立して進化したことが示された。 「今日飛ぶことや食べることに関する多くの同じ問題が1億2000万年前にも存在していた。それが、今日私たちの周りを飛び回る鳥の遠い親戚に、同じ特徴のいくつかが進化した理由だ」とリー氏は語った。 研究チームは次に、同様にかなり長い舌を持っていたと思われる他の数種の化石鳥類を調査し、さらにブレビロストゥラヴィスの標本を探す予定だ。「また、鳥類の鰓上骨がいつ進化したかを特定できるかどうかも調べたい。なぜなら、この骨は現生鳥類の長い舌の形成に極めて重要だからだ」とリー氏は語った。 現生鳥類が舌骨器官をどのように使っているかを調べることで、ブレビロストルアビスが短い鼻と長い舌骨という珍しい組み合わせを進化させた理由も解明されるかもしれない、と現生動物の骨と筋肉がどのように連携して働くかを研究しているカンビック氏は言う。 それでも、ブレビロストルアヴィスのような昔の動物の頭蓋骨や舌の骨から多くのことを学ぶことができると彼は言う。 「(骨は)これらの動物が何を食べていたかという点で、具体的な洞察を与えてくれる可能性があります」とカンビック氏は言う。「そして、それは、体の他の部分の骨から得られる情報よりも直接的に、動物の日常生活に関する情報を与えてくれるのです。」 |
<<: X線検査により1545年の難破船に関する新たな手がかりが明らかに
>>: パーサヴィアランスから採取された最初の火星岩石サンプルが、水問題の解決に一歩近づく
推薦する
陸上に最初に生息した生物は誰でしょうか?
今週、ネイチャー誌に発表された新しい論文は、地球上の生命が正確にいつ初めて陸上に定着したのかという、...
NASAの最新宇宙飛行士たちに会いましょう
この投稿は更新されました。宇宙飛行士になることは、子どものころの夢の仕事です。そして、幸運な、そして...
アポロ1号がなければ、私たちは月に行くことはできなかったかもしれない
宇宙飛行士ガス・グリソム、エド・ホワイト、ロジャー・チャフィー。この3人の宇宙飛行士はアポロ1号の火...
5つの星からなる太陽系は「スターウォーズを凌駕する」
今週ウェールズのランディドノで開催された英国国立天文学会議で発表された研究によると、研究者チームは2...
舌が味覚を脳に伝える仕組み
ナッツの風味がする熟成チーズから、ダークチョコレートのフローラルな味わいまで、おいしい味が絶えず私た...
反物質は下に落ちるのか、それとも上に落ちるのか? 明確な答えが見つかりました。
アルバート・アインシュタインは、一般相対性理論を思いついたとき、反物質の存在を知りませんでした。一般...
この幅43マイルのクレーターは22億年前にできたもので、地球最古の隕石衝突である。
ヤラババ クレーターは、隕石によって形成された地球の空洞としては珍しい存在です。オーストラリア西部の...
人間は走るときに自然にエネルギー効率の良い速度に落ち着く
ジョギングをするとき、人は走る距離に関係なく、自動的にエネルギー効率の良い走行速度に落ち着くと科学者...
今年は宇宙が話題をさらいました。お気に入りの記事はこちら
この10年間、私たちの頭上では多くの出来事がありました。NASAや他の宇宙機関は、氷の衛星から準惑星...
宇宙飛行士スコット・ケリーの次なる目標は?
今日の午後、宇宙飛行士スコット・ケリーは国際宇宙ステーションに別れを告げる。それは地球低軌道上にある...
NASAの双子の月探査機が月面への衝突に成功!
月周回軌道上で350日間を過ごした双子の探査機「エブ」と「フロウ」は、本日、綿密に計画された月の北極...
ブロントサウルスは実在し、名前が復活
恐竜といえば、ティラノサウルス・レックスとヴェロキラプトルのバイク乗りが注目を集めるかもしれません。...
今夜のふたご座流星群で宇宙の岩石が花火になる様子をご覧ください
毎年 12 月になると、最も確実に見える流星群の 1 つであるふたご座流星群が地球に戻ってきます。今...
ビッグバンの重要な部分は依然として解明されていない
すべては爆発とともに始まりました。想像を絶するほど短い一瞬の間に、初期の宇宙は想像を絶する速さで膨張...
この新種の恐竜はゴーストバスターズのズールに似ている
ズール・クルリヴァスタトルの頭蓋骨。ブライアン・ボイル © ロイヤル・オンタリオ博物館新しく発見され...