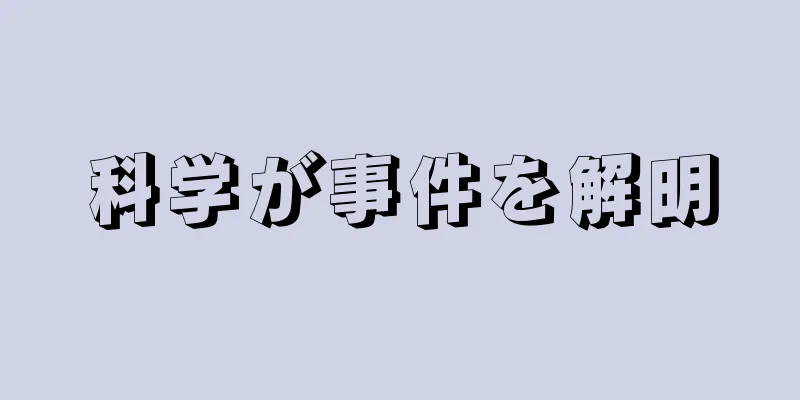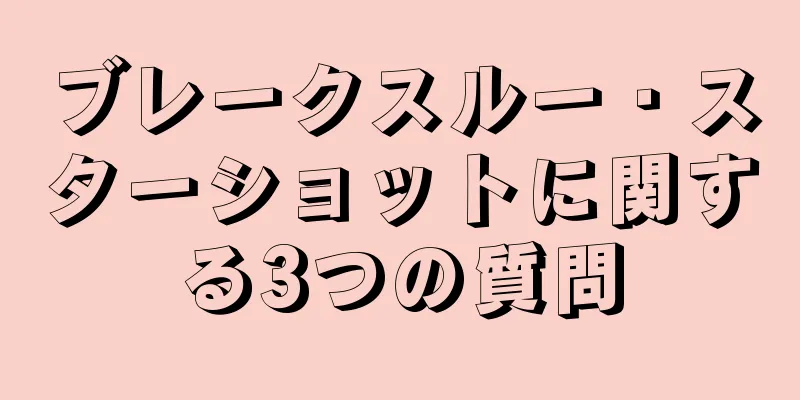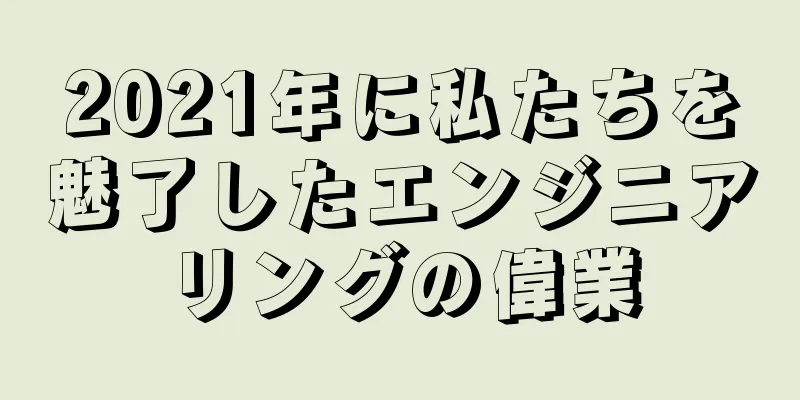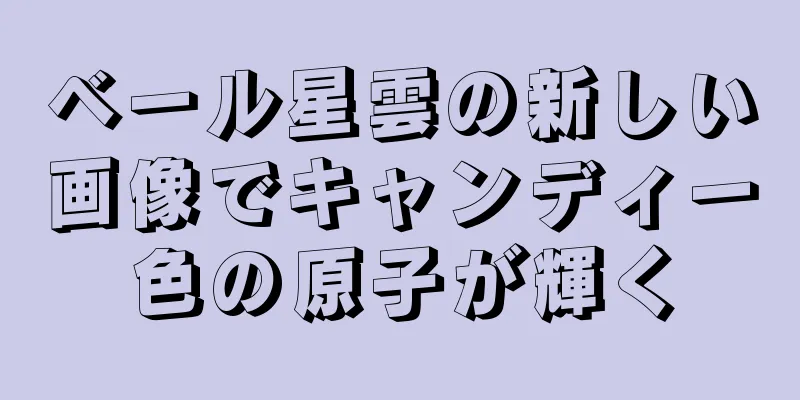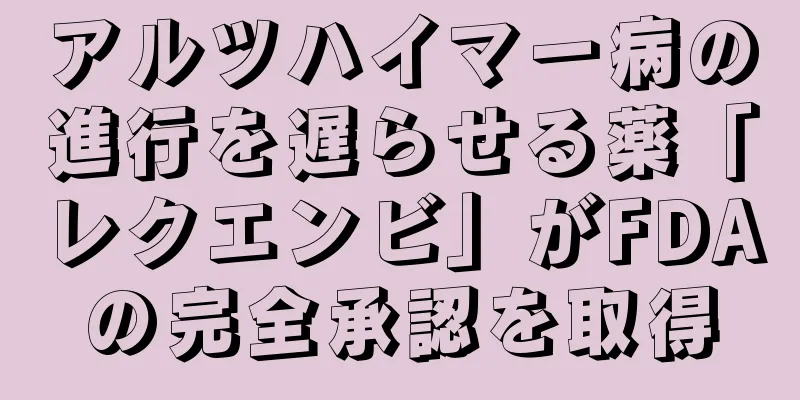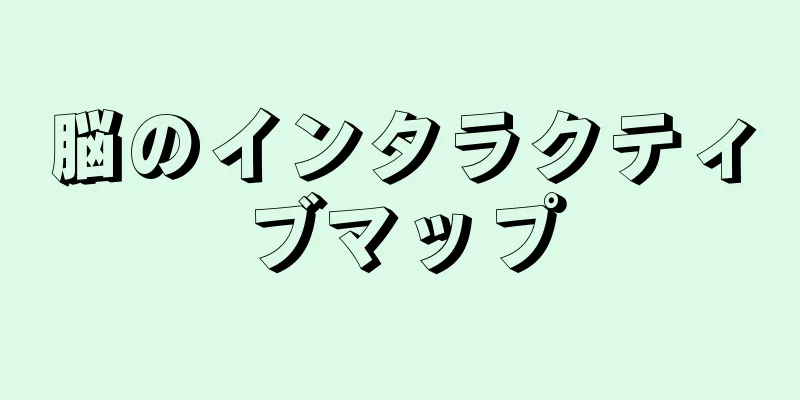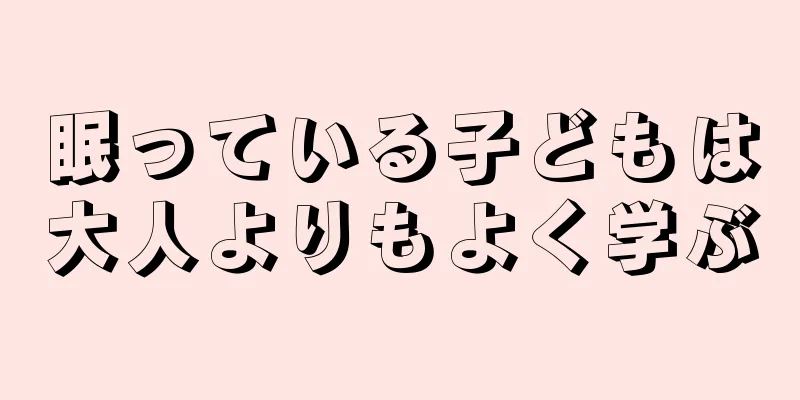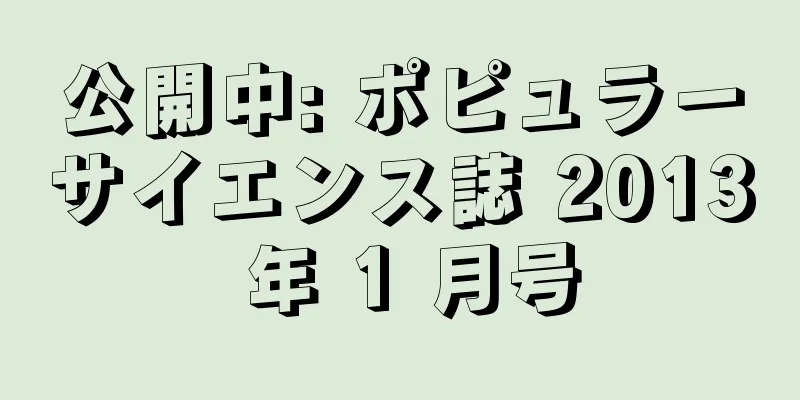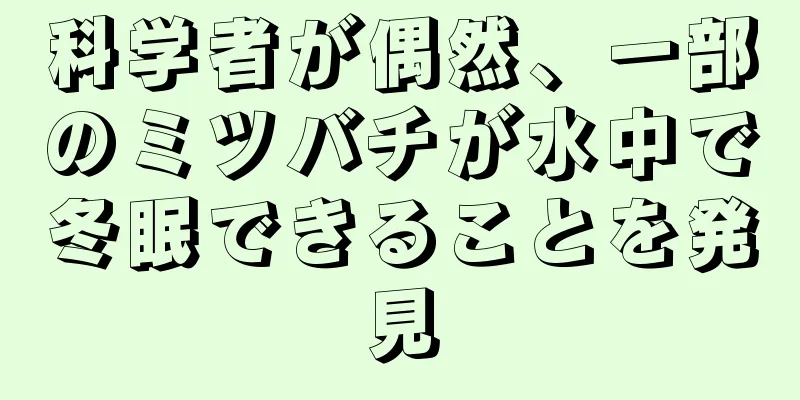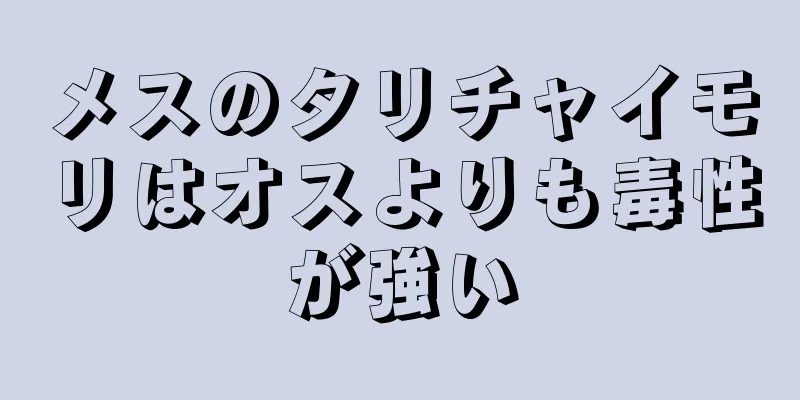億万長者のピーター・ティールは老化との戦い、腐った食品の検出などに投資している
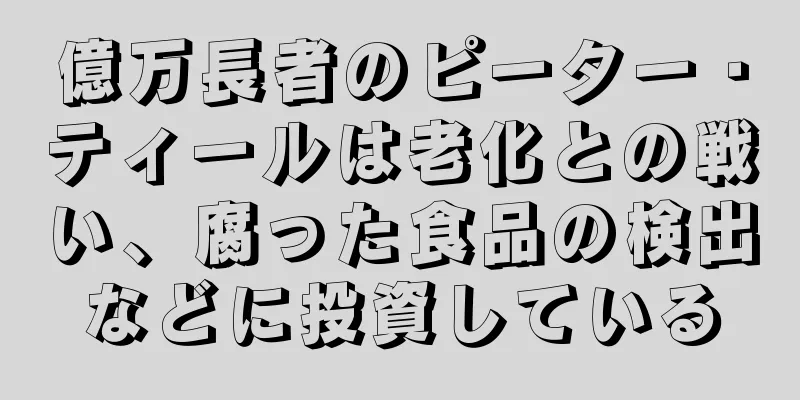
|
今年初め、PayPal の共同創業者で億万長者の投資家ピーター・ティールが設立した子会社組織 Breakout Labs は、アイデアの推進のために資金提供を受けるバイオテクノロジーの新興企業を厳選して数社発表した。Breakout Labs の使命は、「急進的な科学的進歩」を主流にしたいと考えている企業に投資することであり、資金不足の優れた発明を最大 35 万ドルまで支援する (Breakout Labs からのコンサルティング支援も含む)。 さて、ブレイクアウト ラボが今年 2 度目のベンチャーへの資金提供を発表して、またやってきました。今回のアイデアは、ヤモリの皮膚を模倣した接着剤、食品が腐っているかどうかを判断できる低コストのセンサー、水をはじく金属、老化と闘うミッションなど多岐にわたります。今回の発表の全体的な傾向は、微細構造の進歩への資金提供です。3 つの企業がナノスケールの機械的イノベーションを使用して、材料の特性を変えているように見えます。 世界を変える可能性のある次のプロジェクトについて、さらに詳しくご紹介します。 ナノグリップテックヤモリは、ほとんどどんな表面でも登ることができ、壁や天井を比較的簡単によじ登ることができます。これは、ヤモリの足が多孔質の素材につかまる微細な毛で覆われているためです。NanoGriptech はこのアイデアを利用して、粘着剤の跡を残さずにつかむ素材を開発しています。同社はこの乾燥接着剤を Setex と呼んでおり、繰り返し使用でき、圧力に敏感です。顕微鏡で見ると、Setex はキノコ型の吸盤が均一に並んでいるように見えます。吸盤は表面につかまり、元の長さの 700 パーセントまで伸びて表面にくっついたままになります。これらはポリウレタンで作られています。 NanoGriptech は、コンピューターや家具の製造、医療、ロボット工学などの分野で Setex が応用されると考えています。ピッツバーグに拠点を置く同社は、Setex の指先を備えたロボットが (ロボットにしては) 繊細に本のページをめくる様子を映したビデオも公開しました。 C2センスケンブリッジに拠点を置く C2Sense のおかげで、匂いで検査する時代はもうすぐ終わるかもしれない。MIT の Swager 研究室で開発されたこの技術は、カーボンナノチューブを使って食品が腐ったことを知らせる。基本的に、このセンサーは 2 つの電極の間にある非常に感度の高いカーボンナノチューブの束である。ナノチューブが空気中のカビなどの特定の物質と接触すると、ナノチューブに付着して電流が変化する。C2Sense によると、クレジットカードほどの大きさに 30 個のセンサーを収めることができるという。 このセンサーは、わずか 0.00001 ワットという驚異的な低エネルギー消費量で、腐った食品から放出されるエチレン、アミン、その他のガスを 100 万分の 1 未満の濃度でも検出できると C2Sense は述べています。 サイトジェングーグルのカリコ・ラボは2013年に「死を治す」と発表して話題になった。現在、ティールは同様のミッションに投資している。サイトジェンは、老化は身体の特定の部分の衰えではなく、全体的なプロセスであるという観点から老化に取り組んでいる。 「加齢は必然的に、パーキンソン病やアルツハイマー病、その他の病気につながるような肉体的、精神的な衰えをもたらすという思い込みがあります。しかし、証拠はそうではないことを示しており、それが私たちがCyteGenを立ち上げるきっかけとなりました」と、CyteGenの共同創設者兼社長であるジョージ・ウグラス氏は語った。 CyteGen は技術面では秘密にしているが、8 つの大学から集まったチーム メンバーは神経変性疾患に焦点を当てる予定だ。CyteGen という名前は、個々の細胞の染色体構造を研究する細胞遺伝学の分野とよく似ている。 マクステリアル株式会社現代社会は金属で作られています。鋼鉄の桁は超高層ビルの背骨として機能し、金属の橋脚や杭がなければ橋はこれほど長くも広くもなりません。しかし、露出した金属には錆という固有の問題があります。Maxterial Inc. は金属の外側の層を再設計することで、実際に液体をはじく材料を生み出しました。この特性を持つ材料は疎水性と呼ばれますが、現在、疎水性にするための最も一般的な方法は、撥水コーティングをスプレーすることです。 Maxterial は、外側のコーティングに小さな空気ポケットを設けて表面積を減らし、水が付着しないように設計しました。この技術により、構造物の氷形成と腐食を軽減できると、彼らは考えています。このアイデアを持つ研究者は彼らだけではないかもしれません。ロチェスター大学が開発し、1 月に発表した同様のコンセプトでは、レーザー エッチングを施した表面が同様に水をはじくという詳細が説明されていますが、ロチェスター チームは逆の効果、つまり重力に逆らって水が這い上がる表面を作り上げました。デモ ビデオでは、水分が付着しない調理鍋に使用されている撥水技術が紹介されています。 しかし、ブレークスルー ラボは、マクステリアル社がロチェスター大学の研究の 2 年前に自社の技術に関する情報を公開しており、競合他社よりも持続可能かつ低コストで大規模生産できると指摘しています。この技術がより広く利用可能になったときに、この主張がどのように実現するかがわかるでしょう。 次の資金調達ラウンドBreakout Labs はすでに 26 社に資金提供しており、さらに資金提供先を常に探しています。オンライン フォームから問い合わせを送信できます。完全な申請書が必要な場合は、30 日以内に提出する必要があります。完全な申請書には、科学的概要、ミッション ステートメント、略歴、その他の外部資金援助の完全な開示が必要です。 ブレークスルーラボから提供されたマクステリアルに関する詳細情報を追加して更新しました |
<<: このシミュレーションされたネズミの脳は素晴らしいが、脳の謎は解けない
>>: 物理学者らが62マイル離れた場所に量子テレポーテーションで情報を伝える方法
推薦する
2024年までに月に戻るNASAの混乱した計画の内幕
1972年以来初めて人類を月に送り込むことを目指しているNASAのアルテミス計画は、予算を大幅に超過...
参考までに:どの種類の恐竜の肉が一番美味しいでしょうか?
オルニトミムス科として知られるダチョウに似た恐竜は、独特の恐竜の味を保ちながら、おそらく最も消費者に...
オーシャンシティの遊歩道を巡回する夏の鳥たち
ニュージャージー州オーシャン シティのビーチ タウンにひっそりと佇む、何の変哲もない別荘が、バケーシ...
超薄型の「ミラー膜」が宇宙望遠鏡の大型化につながる可能性
史上最大の望遠鏡の鏡を宇宙に打ち上げるのに、何年もの設計とエンジニアリングの苦労を要しました。現在、...
オウムアムアは宇宙人ではないが、小惑星でもないかもしれない
小惑星や彗星は重い傾向があるが、太陽系を通過するのが初めて確認された恒星間訪問者であるオウムアムアは...
2017年の皆既日食のベスト写真
全米各地のアメリカ人が2017年8月21日を心待ちにしていたが、それには十分な理由があった。今日の午...
植物が遺伝的記憶をどのように伝えるのかがついに解明される
動物が生まれたり、植物が芽生えたりすると、新しい生物は親の DNA だけでなく、エピジェネティック記...
大量絶滅は地球上の生命をより多様化させたが、再び
過去 5 億年の間に、地球は何度も大量絶滅に見舞われ、地球上のほとんどの種が絶滅しました。そしてその...
居住可能な冷たい巨大惑星の数を過小評価している可能性がある
宇宙のどこかに、地球と太陽の距離の2倍ほども離れた恒星から離れた岩石惑星があるかもしれない。恒星の暖...
2012 年 2 月 6 日~10 日の今週の最も素晴らしい科学画像
今週のまとめには、驚くべき画像が多数あります。火星にかつて巨大な海があった可能性、紫色のリス、驚くべ...
NASA の最大の失敗から、完璧な人間の視覚を実現するツールが生まれた
技術移転ポピュラーサイエンスハッブル宇宙望遠鏡が瞬きしてぼんやりとした空を見た日から、望遠鏡の光学の...
人間とイルカが一緒に魚釣りをすると、両者とも勝利する
研究者たちは10年以上にわたり、ブラジルの2大捕食動物である人間とイルカの漁業慣行を研究してきた。2...
地球上で最も深い地点を地図化する海洋地質学者に会う
ドーン・ライトがほぼ破壊不可能な部屋で世界の底に急降下したとき、海の深い闇は彼女に宇宙の広大な暗闇を...
宇宙採掘は合法ですか?
もし人類が惑星間を行き来する種族になるとしたら、太陽系外への拡大はおそらく NASA の資金だけでは...