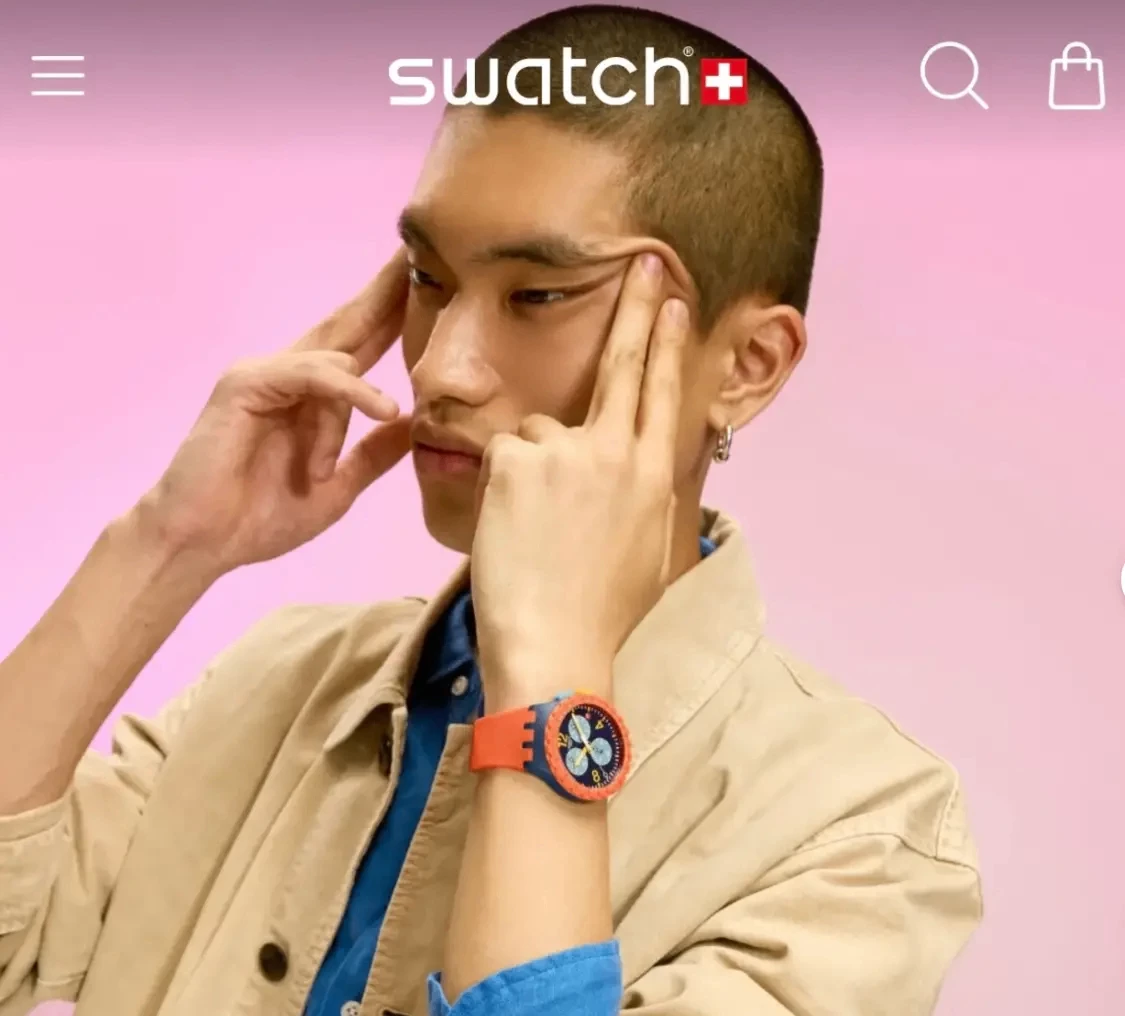日本の生活に欠かせない通貨単位「円」。買い物をするときも、給料をもらうときも、誰もが当たり前のように使っています。しかし、その「円」という名前がどのように生まれたのか、実ははっきりとした答えは残されていません。150年以上続く日本の通貨単位にはいくつもの謎があり、学者や歴史愛好家の間で様々な説が語られています。ここでは、円の成立過程と考えられる3つの仮説を詳しく見ていきます。

近代通貨制度と「円」の誕生
1871年(明治4年)、新政府は「新貨条例」を制定しました。この法律により、日本は近代的な通貨制度を導入し、「円・銭・厘」という十進法の体系を採用しました。それまでの江戸時代では、金貨・銀貨・銭貨が入り混じり、しかも何度も改鋳された結果、同じ「両」でも含まれる金や銀の量が異なるなど、通貨制度は非常に複雑でした。新しい時代を切り開こうとする明治政府にとって、貨幣の統一と近代化は急務だったのです。
このとき、新しい通貨単位として採用されたのが「円」。純金1.5グラムを1円とし、在来通貨の「一両」をそのまま「一円」と見なすことが定められました。当初の表記は漢字の「圓」であり、現在の「円」という字が正式に登場したのは戦後の昭和期からです。
「円」という名前に関する三つの説
1. 「名は体を表す」説
明治初期の会議で、大隈重信が「新しい貨幣は円形にすべき」と提案したという逸話が残っています。大隈は指で丸を作り、「子供でもこの形を見れば貨幣だと分かる」と主張しました。つまり、貨幣の形が円だから、その名前も「円」にすべきだ、という考え方です。十進法の導入と合わせて、合理的な近代化の象徴として「円」という名前が選ばれたのではないかという説です。
2. 香港から伝わった「一円」の影響説
もう一つ有力とされるのが、香港の造幣局から輸入された造幣機械の影響です。当時、香港では「香港一円」と刻まれた銀貨が流通しており、日本もそれを参考にした可能性が高いといわれています。実際、日本で最初に作られた一円銀貨の重さや品位は香港の銀貨と同じでした。つまり、「円」という呼称は国際的に分かりやすい単位として採用された、という解釈です。
3. 江戸時代の知識人がすでに「円」と呼んでいた説
さらに興味深いのは、江戸時代の一部で「両」を「円」と呼んでいたという説です。中国から伝わった影響や、庶民の間で流行した「持丸長者」という言葉などが背景にあります。「丸」や「円」が金銭を意味する言葉として自然に使われていたため、新しい通貨単位も抵抗なく「円」と受け入れられたのではないか、と考えられています。
消えた資料と残された謎
残念ながら、明治初期に発生した火災によって紙幣寮や皇居に保管されていた重要な文書が焼失してしまいました。そのため、「円」という呼称がいつ、誰によって、どのように正式決定されたのかは今も明らかになっていません。ただし、これら三つの説を合わせて考えると、「円」という名前は自然な流れの中で誕生したと考えるのが妥当でしょう。
現代に続く「円」の重み
150年以上の歴史を経て、「円」は日本経済の基盤として揺るぎない存在になりました。戦後の混乱期や高度経済成長期、バブル崩壊やリーマンショックといった世界的な経済危機を乗り越えてきた通貨単位です。現在も国際通貨の一つとして認められ、円相場は世界の金融市場に大きな影響を与えています。
私たちが普段何気なく使っている「円」には、このように多くの歴史と謎が秘められています。明治の人々が目指した合理性や国際性、そして庶民の生活感覚が交わって生まれたのが「円」だったのかもしれません。