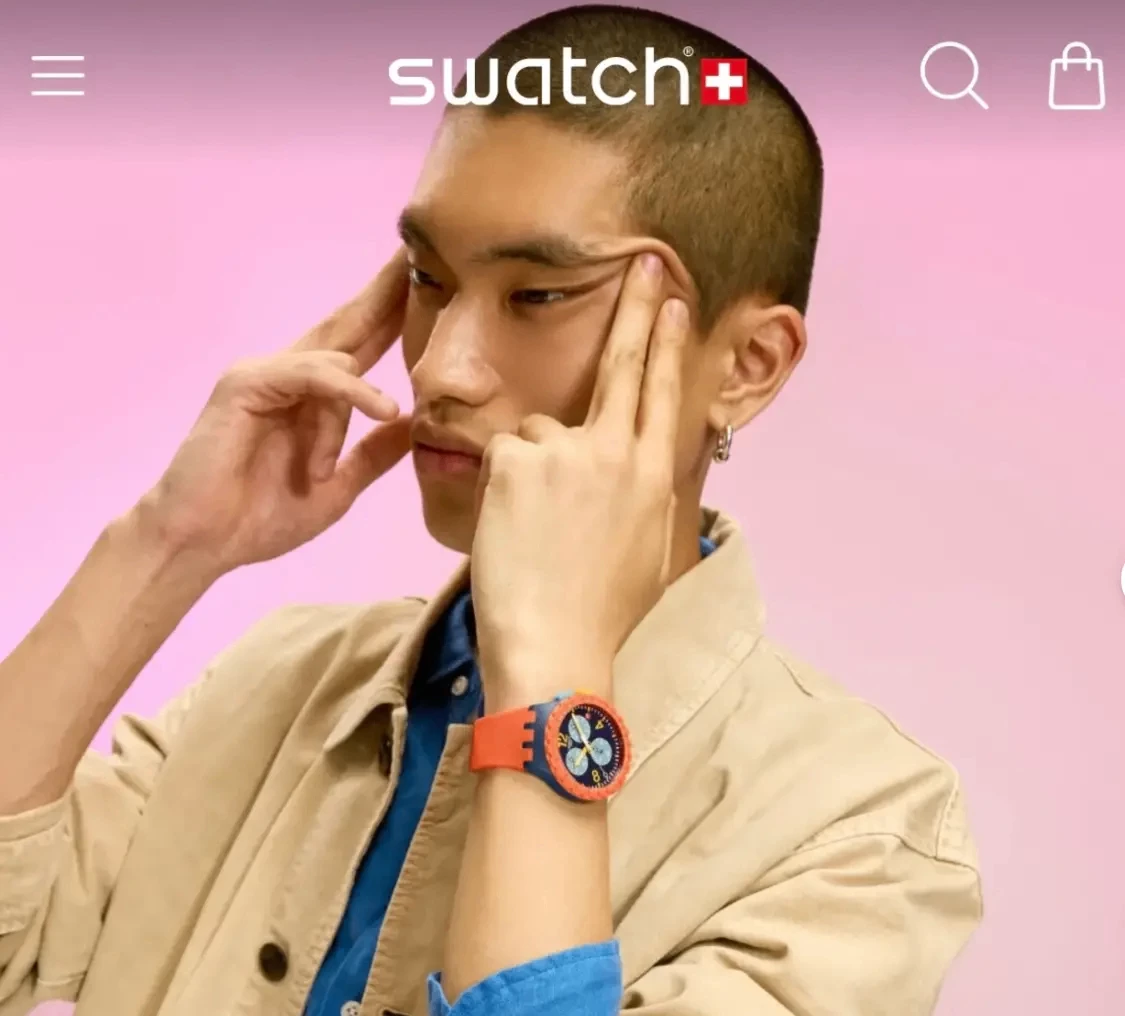日本経済新聞は8月18日、日本の金融庁が今秋にも初の円建てステーブルコインの発行を承認する見通しだと報じた。狙いは、国際送金やブロックチェーンを基盤とした資産管理サービスへの活用である。

この新しい通貨を発行するのは、東京に本社を置くフィンテック企業 JPYC株式会社。同社は8月中に資金移動業者として正式に登録される予定で、発行されるステーブルコインは「JPYC」と名付けられる。1JPYCは1円と等価で交換され、円建ての預金や日本国債といった流動性の高い資産が裏付け資産となる。
背景:ドル建てから円建てへ
ステーブルコインとは、ブロックチェーン上で発行され、ドルや円といった法定通貨に価値を連動させた暗号資産の一種である。発行体は少なくとも1対1での準備資産を保有し、価格の安定性を担保する。米ドルに連動する「テザー(USDT)」や「USDコイン(USDC)」はすでに世界的に普及しており、2025年7月時点で流通総額はおよそ2500億ドル(約39兆円)に達している。
日本では2023年6月の改正資金決済法により、ステーブルコインを「本邦通貨建て資産」と定義。他の暗号資産と区別したうえで、銀行・信託会社・資金移動業者による発行を認める制度が整備された。今回のJPYCは、この法改正に基づく最初の本格事例となる。
想定される利用シーン
個人、企業、機関投資家はJPYCを購入して電子ウォレットに保有でき、送金や決済に利用可能だ。特に想定されているのは以下の用途である。
海外留学生への仕送りや国際送金
企業間取引やサプライチェーンでの支払い
ブロックチェーンを活用した資産運用やデジタル証券の管理
JPYCの発行規模は、3年以内に総額1兆円(約4870億円)に達する計画が示されている。
国債市場への影響
JPYCの普及は、日本の国債市場にも影響を与える可能性がある。JPYC代表の岡部氏(音訳)はSNS「X」で、ドル建てステーブルコインの発行体が米国債の大口購入者になっている事実を指摘。USDTやUSDCは米国債を主な裏付け資産として保有しており、結果的にアメリカ国債市場を支えている。
同様に、JPYCが広く利用されれば、日本国債の新たな需要源となる可能性がある。岡部氏は「将来的にJPYCが大量の日本国債を購入するシナリオも十分に考えられる」と語った。
国際的な懸念
一方で、ステーブルコインには課題も多い。国際決済銀行(BIS)は2025年6月の年次経済報告で、特に分散型ステーブルコインの問題点を強調。中央銀行による裏付けがないこと、不正利用への対策が不十分であること、融資を通じた信用創造機能を持たないことの3点を主要な欠陥として挙げた。
こうした国際的な指摘は、日本円建てステーブルコインの普及と金融システムへの影響を議論するうえで、無視できない要素となるだろう。
今後の展望
日本初の円建てステーブルコイン「JPYC」の登場は、デジタル金融の新たな一歩となる。しかし、その安定性、規制のあり方、そして国債市場や国際金融秩序への影響については、今後も慎重な検証が求められる。
日本がドル一強のステーブルコイン市場にどこまで存在感を示せるのか、そして「円デジタル資産」が国際送金や資産運用の分野でどのように受け入れられるのか、世界が注目している。